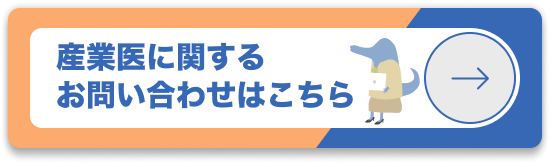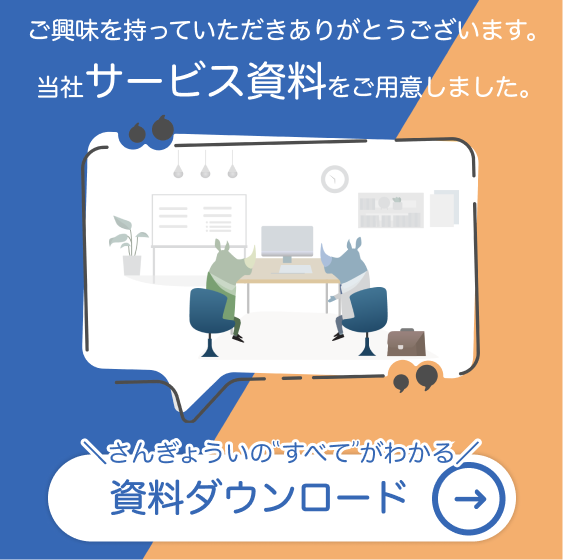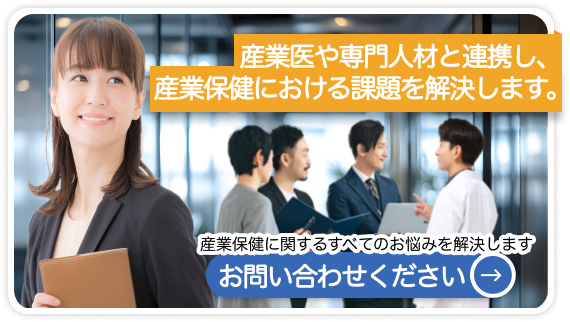糖尿病と仕事の両立支援~温かな対話から見えた現場のリアル~

6回にわたり糖尿病と仕事との両立支援について綴ったコラムを掲載してきました。産業現場で働く方々にとって、病院で治療を続けるだけではなく、仕事の中で安全かつ持続的に働くためのサポートが不可欠となります。コラムを作成する過程で日々の産業保健活動で感じていること、特に産業医として執筆いただいた先生は臨床医でもあるため両方の視点も含めて語っていただいております。
今回は、コラム作成をした産業医と保健師が振り返りの対談を行い、その内容をまとめた番外編コラムをお届けします。
糖尿病と仕事の両立支援~温かな対話から見えた現場のリアル~
日本人の健康課題として「糖尿病」が増えています。多くの場合、糖尿病はただ数値が高いというだけで片付けられがちですが、実際には日々の食事、睡眠、運動といったライフスタイル全体の積み重ねから生じる複雑な疾患です。
産業医は「臨床場面での診察では、必ず患者さんの表情を見て、聴診器を手にして直接患者さんの体や生活に触れます。しかし、職場での対応は、必ずしもそのような丁寧な接遇ができるわけではなく、数値だけを頼りに判断されがちだ」と述べます。一方、保健師は「糖尿病は血糖値が高いという ‘氷山の一角’ に過ぎません。患者さんの生活習慣や職場環境、本人がどのような気持ちで働いているかを、じっくり聞き取ることが大切」と語ります。
保健師は過去の体験した事例を語りました。健康診断で高血糖が指摘されたものの、本人は『ただの健診結果』と受け止め、定期受診にも乗り気ではなかったというケースがありました。そこで現場の産業医は、企業内での安全配慮義務や、もし万一の事態が起これば家族にもリスクが及ぶことを丁寧に説明しました。さらに、保健師が職場の状況や本人の普段の生活習慣について細かく訪ね、双方が連携して「この人は半年間、主治医と一緒に継続的にフォローしなければ安全に働けない」と判断するに至りました。結果、当初は受診に消極的だった本人も、家族や職場仲間の支えを実感し、勇気を出して治療を受け始め、食事指導や運動プログラムの導入によって血糖値も徐々に改善していったのです。
執筆した産業医は、現場の産業医への期待を語り、「産業医の役割は医療機関の主治医と適切に連携・ 情報共有を行うことで、社員の健康(医療)情報を、職場で必要な配慮の内容へ翻訳する機能を果たすことです。社員が糖尿病にあることを把握し適切に対処するためには、検査データの確認だけでなく、企業で働く実情、たとえば残業時間や仕事の負荷、上司・同僚とのコミュニケーションなど、数多くの要素が絡み合っているので、それらを踏まえた上でどうしたら安全に継続的に働くことができるか、職場にアダプテーションできるかを考えることが産業医の役割となります。そのためには、社員へ温かな眼差しと共感をもってハートへアプローチする視点が欠かせないのではないか」と述べています。これに対し、保健師は「私たちが現場でできることは、ただ情報を集めるだけでなく、働く人々の『生きる力』に寄り添うことです。『どうしてこんな数値になったのか』『あなたはどんな環境で働いているのか』と、まずは本音の対話から始めるのです」と応じます。
現実問題として、企業の健康診断は年に一度、または数回実施されるものの、その結果だけでは、その背景にあるライフスタイルの変化や職場環境のリスクを十分に捉えることは難しいのが実情です。
たとえば、ある若手社員は「前回よりも血糖値が上昇しているが、日々の業務に追われて体調の変化に気づかなかった」という声がありました。産業医はこうしたケースに対して「高血糖は糖尿病の始まりであり、これを放置すればいつか重篤な合併症に発展するリスクがある」と危機感を示し、保健師は「まずは、本人とじっくり話し合い、家庭や職場でのストレス要因や食事内容を一緒に見直しましょう」と提案します。
また、両者が強調するのは「対談」や「対面での面談」の重要性です。
産業医は「安全に働ける状態をつくるには、医師としての意見をしっかり伝えるために、必ず本人と直接会って面談することが必要不可欠です。なぜなら数字だけで判断するのは社員の状況に沿った就業判断が難しいからです。」と述べています。保健師は、「一方で、私たちは柔らかなアプローチで、まずは『あなたの今の状態はどうですか?』と、心の声にも耳を傾けたい。そして、その人が本当に大切にしているもの、大事にしている価値観を一緒に探る。その価値に気づくと、”自分でどうにかしなくては”という前向きな気持ちが芽生えるのです。」と、共感をもって語ります。このような歩み寄りのプロセスは、社員の情報を集めやすくします。そしてその情報を産業医に伝えることで、本人の治療と仕事の両立の仕方、会社側の配慮の方向性が異なってきます。
たとえば、ある社員は、糖尿病の症状が進む中で職場に対する不安を抱えていました。担当の産業医が何度も面談を重ね、保健師が職場の仲介役として、上司や同僚との情報共有を促しました。結果として、社員は自らの健康リスクを正しく認識し、主治医との連携の下、生活習慣の改善に取り組むようになったのです。仕事に不安を抱えながらも、周囲の支援を実感したことで、徐々に「働くことの意味」や「自分の大切な価値」に向き合うようになりました。
こうした対話の現場から見えてくるのは、糖尿病の両立支援において、単にデータや検査結果を示すだけではなく、一人ひとりの生活背景、仕事に対するモチベーション、さらには家族や仲間とのつながりを大切にすることの重要性です。数字だけでは測れない心の部分に寄り添い、双方の視点―厳しさと温かさ―を融合させることで、働く人々は「健康でありながらも安心して仕事に打ち込める環境」を手にしていくと考えます。
私たち産業医と保健師は、たとえ忙しくても、冷静なデータと温かい対話という両輪で、今日もまた一人ひとりの健康支援に取り組むことが必要と考えます。
もしあなたが今、職場での健康管理に悩みや不安を感じているなら、どうか自分自身の価値を再確認し、周囲に相談する勇気を持ってほしいと思います。数字はただの指標にすぎません。その裏にある、あなた自身の今の状況や熱い気持ちをくみ取り、共に歩むパートナーが必ずいます。
このように、糖尿病と仕事の両立支援は、医療現場だけでなく、企業や地域全体の支え合いの中で成り立っています。専門知識と温かい人間性が融合すれば、どんなに厳しい状況も乗り越えられる―そんな希望を、これからも多くの人々に届けていきたいと、私たちは心から願っています。
看護師の後、働く人の健康管理に携わるため保健師として産業保健業務に従事する。
現職では、さまざまな規模の企業に対して、個別支援を中心としたかかわりから、広く集団に向けて健康情報の発信や、喫煙対策プログラム構築、保健師の導入支援など産業保健サービスに携わる。
北海道の拠点病院で糖尿病指導医として勤務。
日々の診療から予防医療の重要さを感じ、産業医も開始。産業医、地方労災医員の活動から診察室と職場をつなぐことの重要性を感じ、これまでの知見をまとめ情報発信を行う。
【関連コラム】