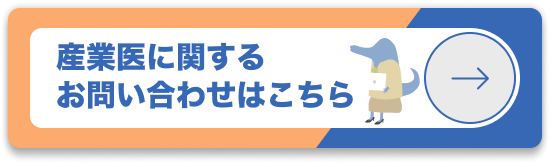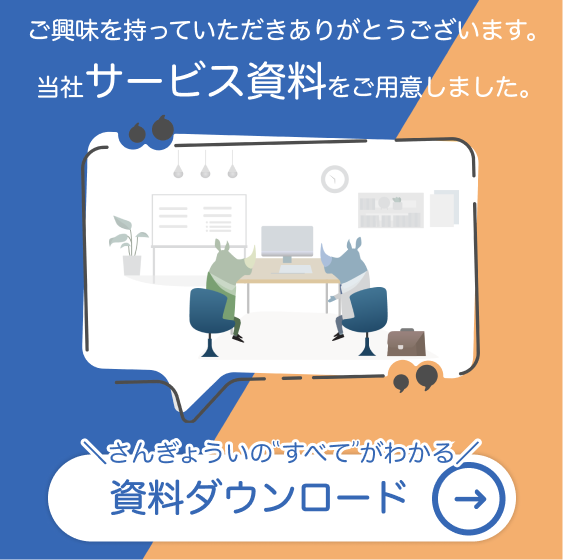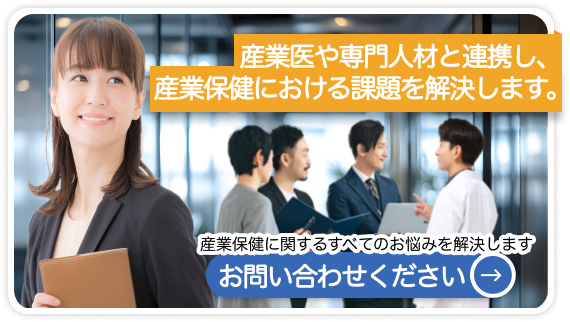産業医面談の課題を整理し「義務」から「戦略的投資」へ変える体制づくり

「いま行っている産業医面談、このままで本当に意味があるのだろうか?」
そう感じたことのあるご担当者は少なくありません。実際、「最低限の対応しかされない」「知りたい情報が引き出せない」といった不満から、産業医の交代を検討する企業も見られます。
さらに2015年の労働安全衛生法改正により、従業員50人以上の事業場ではストレスチェックと高ストレス者への産業医面談が義務化されました。しかし、形式的な運用では、企業が期待する成果につながらず、制度の形骸化が課題となっています。
本記事では、産業医面談の基本から現場の課題を整理し、義務対応にとどまらず経営に資する仕組みへと進化させる方法を、3つのカテゴリーに分けて解説します。
目次
- 産業医と産業医面談の基礎知識
- 産業医面談の「現実」と改善のための方向性
- 産業医面談を3つのカテゴリーから整理する
- 産業医面談カテゴリーを横断したフロー整備の重要性
- 産業医面談は「義務」ではなく「戦略的投資」へ
産業医と産業医面談の基礎知識
まずは、産業医の役割や産業医面談の法的な位置づけについて確認しておきましょう。制度の基本を押さえることで、後の課題や改善策をより具体的に捉えることができます。
産業医の職務
産業医は、労働安全衛生規則第14条第1項に基づき、健康診断や面接指導とその結果に基づく措置、作業環境や業務の管理、健康相談や教育、衛生教育、さらに健康障害の原因調査と再発防止を担います。従業員の健康維持と職場の安全確保を通じ、組織全体のリスク低減と生産性向上に貢献する役割を持っています。
産業医面談の「現実」と改善のための方向性
産業医面談は、法令で実施が義務付けられている面談と、企業の判断で行われる面談があります。前者は、「長時間労働者に対する面談(面接指導)」および「高ストレス者への面談」が該当し、いずれも労働者本人の希望があった場合、企業には実施義務があります。
企業の現場では、安全配慮や健康増進などの視点から、以下のようなケースでも面談が多く実施されています。
- 休職・復職時の面談
- 従業員の体調不良(メンタル・フィジカル)に関するフォロー面談
- 健康診断後のフォローアップ
- 管理職からの相談に基づく個別面談 など
これらの面談は、対応方法が不明確なまま産業医に丸投げされるケースも多く、課題が顕在化しやすい領域です。
この記事では、産業医面談を企業価値向上に貢献する、より実効性のある場として改善するために、産業医面談を3つのカテゴリーに整理し、各カテゴリーを横断したフローとして整備することの重要性を解説します。
その本題に入る前に前提として、まず産業医面談の「現実」を産業医の声をもとに分析します。これは、さんぎょうい株式会社が多くの産業医と接するなかで、よく聞く「現場の声」です。
産業医に求められることが激変している
現在、産業医に求められる役割は大きく変化しています。従来のように、健康診断の結果確認や長時間労働者への面談対応にとどまらず、より複雑で繊細な対応が求められるケースが増えています。
特に増加傾向にあるのが、メンタルヘルスの不調を抱える従業員への面談対応です。
このようなケースでは、単に体調の回復状況を確認するだけでなく、職場環境や人間関係、潜在的なハラスメントの有無など、多角的な視点からの把握が必要になります。
長時間労働のように、時間という明確な指標があるケースと違い、メンタル面の課題は背景が複雑で、対応の難易度も高まります。加えて、面談結果が復職判断や職場改善の基礎資料になることもあり、産業医に求められる責任の重さも増しています。
こうした状況のなかで、産業医本人が感じる負荷も大きくなっています。「これは、もはや一人の産業医が背負うには重すぎる」という声も少なくありません。
このように、産業医の役割が広がる一方で、面談の前提となる情報や企業側の協力体制が十分に整っていなければ、面談の効果も限定的なものになってしまいます。
だからこそ企業側としては、産業医が必要とする情報を適切に提供し、面談を効果的に進めるための体制づくりに目を向けることが求められます。
産業医面談を3つのカテゴリーから整理する

産業医面談には大きく3つの種類があり、それぞれ発生条件や課題が異なります。
この章では「法令で義務付けられている面談」「企業が対応すべき健康・労務問題に関する面談」「従業員の申し出による面談」という3つのカテゴリーに分けて整理し、実務で役立つ視点を解説します。
ご自身の課題に近いカテゴリーを参照することで、具体的なアクションに繋げやすくなるはずです。
法令で実施が義務付けられている産業医面談
労働安全衛生法に基づき、特定の条件に該当する従業員に必須とされる面談です。対象となるのは主に以下のケースです。
- 長時間労働者に対する面接指導
- ストレスチェック後の高ストレス者への面接指導
- 健康診断結果に基づく事後措置のための面談
【効果的にするポイント】
義務対応が形骸化しやすいため、単なる実施ではなく、現場で使えるマニュアルやフローの整備が不可欠です。スケジュール調整や記録の属人化を避け、情報共有を仕組み化することで、面談の質を高められます。従業員に産業医の守秘義務を周知することも、申出のハードルを下げる重要な要素です。
企業が対応すべき健康・労務問題に関する面談
以下の面談は、企業が突発的に対応を迫られる場面です。
- 休職・復職時の面談
- メンタルやフィジカル不調に関するフォロー面談
- 健診後のフォロー面談
【効果的にするポイント】
課題は、やり方が分からず産業医任せになりやすいことにあります。復職面談では、業務調整や関係部署との連携が不可欠であり、運用ルールや手引きなどのプロセスを標準化し、属人化を防ぐことが企業責任リスクの低減につながります。
従業員の申し出による面談
法令で定められた条件に当てはまらなくても、従業員自身の健康不安を起点に行われる面談です。例として、健診で異常が見つかり、従業員自ら、産業医に相談するケースがあります。
【効果的にするポイント】
法的義務ではありませんが、早期発見・重症化防止、生活習慣改善につながる重要な機会です。安心して相談できる体制を整えることで、人材定着や職場環境改善を通じ、企業価値向上に直結します。
人材不足が課題となる今こそ、従業員の自主的な声を受け止める仕組みづくりが「戦略的投資」として機能します。
産業医面談カテゴリーを横断したフロー整備の重要性
3つのカテゴリーは独立して存在するのではなく、相互に関連しています。
つまり、すべての面談を一貫したプロセスの中で捉え、活用していくことが不可欠です。
3つのカテゴリーを通じたPDCAによる継続改善
3つのカテゴリーに共通して重要なのは、対応するフローを設計・確立し、事前準備をしっかり行うことです。具体的には以下の取り組みが求められます。
- 健康・労務問題発生時のフローや手引きを整備しておく
- フローの中で産業医面談を正しく位置付ける
- 関係者からの情報収集を適切かつ精度高く行う
さらに、フローは整備したら終わりではありません。実際の運用を通じて課題を洗い出し、Plan→Do→Check→Actionのサイクルを回し続けることが重要です。こうすることで、産業医面談を組織課題の解決に直結させることができます。
【お役立ち】体制づくりのヒント
ここでは、産業医面談やサポート体制の改善のために役立つ具体的なヒントを紹介します。
面談スケジュール調整にオンライン面談を活用する
「産業医面談で、企業が本当に知りたいことが聞けていない」という声は、さまざまな業界で共通して聞かれます。その背景には、産業医と企業側で十分なすり合わせが行われていないことがよくあります。
産業医面談を有意義なものにするためには、事前の打ち合わせが欠かせません。「会社が用意する情報」「従業員(面談者)が提供する情報」「周囲からのヒアリング情報」など、面談の内容に応じて、情報を事前に収集・産業医と共有します。
しかし、これらを丁寧に共有するには時間と手間がかかります。解決するには、情報共有をルール化・定型化し、「面談の前提情報」が自動的に揃う仕組みを整備することがポイントです。
産業医面談の位置づけを再設計する
全てを産業医任せにせず、企業として面談の目的を明確にし、結果を従業員に対する安全配慮の履行と、職場環境改善につなげるルールを整備します。また、従来の産業医面談に対する「先入観を一旦、棄てる」ことも大切です。ポイントは以下の2点です。
- 産業医面談後の内容を組織内で適切に活用・展開するルールを設ける
- 従業員個人への安全配慮を実施すること、組織改善につなげる視点を持つ
外部の知見や客観的な視点が役立つことも多い
他社事例や専門家の支援を取り入れることで、面談体制の改善や新しい視点の導入につながります。さんぎょうい株式会社では、他業種を含めた豊富な事例や最新の知見のご提供などを、積極的に行っていきます。
産業医面談は「義務」ではなく「戦略的投資」へ

多くの企業では、産業医面談を実施することが法令上の義務として捉えがちです。しかし、長時間労働者や高ストレス者への対応だけでは、その本来の価値を活かしきれません。
産業医面談は、従業員の健康維持にとどまらず、職場環境改善や組織リスクの低減につながる重要な経営資源です。休職者の再休職防止、メンタル不調の早期発見・早期対応、健診後のフォローアップなどを通じて、人的・時間的な損失を防ぐ戦略的投資として機能します。
特に中小企業では、限られたリソースのなかで健康課題に取り組む必要があり、面談体制の整備そのものが経営リスクの最小化に直結します。義務対応にとどまらず、自社の文化や働き方に合わせて内容や運用を設計することが、産業保健を次の段階へ進める鍵となります。
継続的な改善パートナーとして
さんぎょうい株式会社のコーディネーターとの協働が、産業医面談を活性化するヒントになります。
経験豊富なコーディネーターは、労働安全衛生活動を企業文化・風土醸成の取り組みのひとつと考えております。なぜなら、百の企業があれば、百通りの企業文化や風土があるように、産業医面談をより効果的に活用するための最適なフローもまた、それぞれに異なるからです。
コーディネーターは、皆さまの企業が新たな産業保健の土壌を育むための心強い伴走者として、企業が目指す方向性を深く理解し、産業医をはじめとする関係者の意思疎通を図ります。
さらに、日々産業保健の新しい情報に触れ、複数の他社事例を持つ私たちだからこそ、社内ではなかなか発言しづらいような内容にも、一歩踏み込んで意見を述べられるというメリットもきっと感じていただけるはずです。
私たちさんぎょうい株式会社は、企業の成長と、そこで働く皆さまの働きがいが両立する未来を支援することをミッションとして活動しています。コーディネーターは、企業の皆さまの実情や課題に寄り添い、企業のリスクヘッジや、従業員が働きやすい環境づくりに伴走します。
ぜひ、さんぎょうい株式会社のコーディネーターにご相談ください。皆さまとの出会いを心よりお待ちしております。