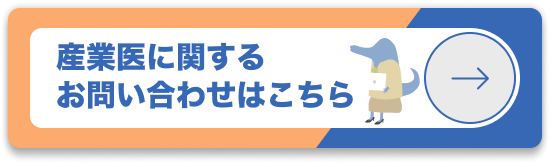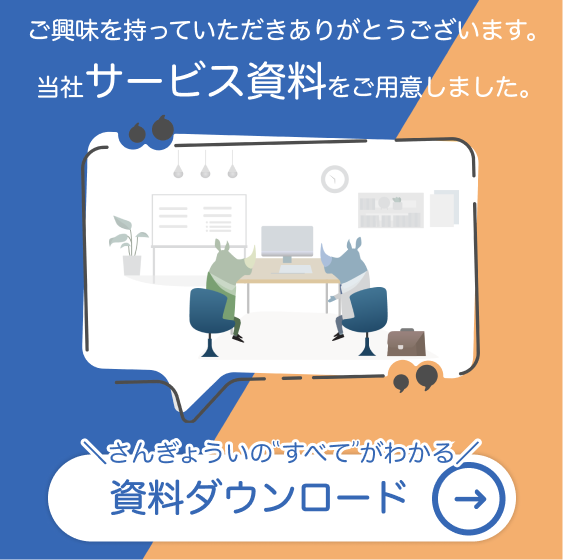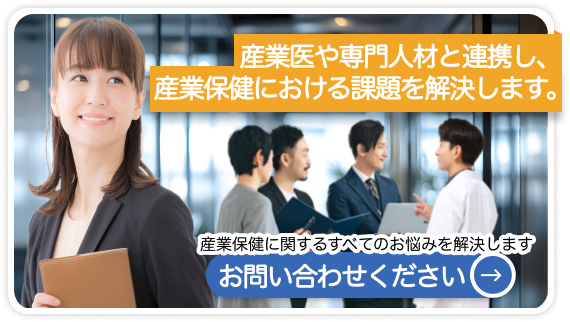第6回 総括コラム: 「働く糖尿病患者の治療と職場支援の最前線」

目次
はじめに
糖尿病は、現代社会において深刻な健康課題であり、個人の生活や職場環境においても大きな影響を及ぼしています。特に働く世代では、糖尿病を抱えながら仕事を継続するために、治療と職業生活の両立が重要なテーマとなっています。第1回から第5回までの内容では、糖尿病の基本的な理解からその職場環境における影響、産業保健スタッフの役割、そして治療と仕事を両立するための具体的な支援策について詳しく解説してきました。
本稿、第6回ではこれまでの内容を振り返りながら、糖尿病患者が職場で安心して働ける環境を整えるためのポイントを再確認します。
第1回 糖尿病と職場環境の現状
糖尿病の社会的影響
糖尿病は、血糖値が慢性的に高くなる代謝疾患で、網膜症、腎症、神経障害などの合併症や心筋梗塞、脳梗塞などのリスクを伴う。特に2型糖尿病は遺伝的要因と生活習慣が関連しており、食生活や運動不足、ストレスがリスク要因となる。 世界的に糖尿病患者は増加傾向にあり、日本では約1,000万人が糖尿病を患っていると推定。高齢化社会で糖尿病を抱えながら働く労働者が増加している。
職場への影響
糖尿病の管理には通院や自己管理が必要だが、働き盛り世代では治療の中断や未受診率が高い。職場環境の理解不足が、治療と仕事の両立を困難にしている。職場での無理解や偏見が、患者の精神的負担や職場での孤立感を引き起こすことがある。 政府の「働き方改革実行計画」に基づき、病気治療と仕事の両立を支援する仕組みや産業保健スタッフの役割が重要視されている。
第2回 糖尿病の基礎知識
糖尿病の分類と特徴
1型糖尿病(自己免疫疾患)、2型糖尿病(生活習慣病)、その他の特定疾患、妊娠糖尿病の4つに分類される。2型糖尿病では、インスリン分泌量が発症時点で50%まで低下していることが多く、時間の経過とともにさらに減少する。最終的にはインスリン療法が必要となるケースも少なくない。
治療と管理
血糖管理には、HbA1c(過去数ヶ月間の平均血糖値)が重要な指標。糖尿病の治療には食事療法、運動療法、薬物療法を組み合わせる。インスリン療法やGLP-1受容体作動薬などの新しい治療法も活用され、業務に合わせた治療法の選択支援が求められる。
合併症のリスク
糖尿病は長期的な高血糖状態により、網膜症、腎症、神経障害、心筋梗塞、脳梗塞、壊疽などの合併症を引き起こす。これらは患者の生活の質を大きく損ない、職場環境にも影響を与える。
第3回 糖尿病患者の職場環境での健康管理
職場環境要因
糖尿病患者が直面する職場環境要因には、高温多湿、長時間労働、夜勤、不規則な勤務シフト、ストレスなどがある。これらの要因は血糖管理を困難にし、合併症リスクを高める。
職場での支援の必要性
職場では、糖尿病患者が安心して働ける環境を整えるために、血糖測定、インスリン注射、補食摂取のための場所確保や、柔軟な勤務体制の整備が求められる。また、周囲の理解を促進するための衛生教育が重要。
第4回 糖尿病治療と仕事の両立
医療機関との連携
糖尿病治療と仕事の両立には、職場と主治医の間で情報共有を行い、適切な治療計画と職場環境調整を行うことが必要。従業員が職場の事情を主治医に伝え、主治医が就業可能な条件を企業に伝える仕組みが推奨されている。
緊急時対応
低血糖やシックデイ(感染症や身体的ストレスによる血糖コントロール困難時)に備えた緊急時対応マニュアルを作成し、職場全体で共有することが求められる。ブドウ糖や経口補水液の備蓄、緊急時の連携体制が重要。
第5回 産業保健スタッフの役割
職場での健康支援
産業保健スタッフは、従業員が健康的な職場生活を送れるようサポートする専門家。健康診断結果のフィードバック、健康増進プログラムの企画運営、個別健康相談対応など幅広い活動を担う。
就業制限の検討
糖尿病による就業制限は、安全配慮義務を果たすために重要。産業医が従業員の健康状態や業務内容を総合的に評価し、必要な場合には勤務時間の短縮や業務内容の変更を提案する。
支援体制の改善
職場全体で糖尿病に対する理解を深め、相談しやすい環境を整備することが重要。職場の健康教育や、柔軟な勤務制度、緊急時対応マニュアルの整備が推奨される。
おわりに
糖尿病を抱える社員への支援は、産業保健スタッフの重要な役割の一つであり、職場全体での理解と協力が不可欠です。今後は、医療技術や勤務環境の変化に対応しながら、個々の社員が安心して働ける環境を整備し、治療と仕事の両立を支援することが求められます。糖尿病患者の健康を守る取り組みは、社員一人ひとりの幸福度の向上だけでなく、職場全体の生産性向上や企業の持続可能性にも寄与する重要な施策と言えるでしょう。
看護師の後、働く人の健康管理に携わるため保健師として産業保健業務に従事する。
現職では、さまざまな規模の企業に対して、個別支援を中心としたかかわりから、広く集団に向けて健康情報の発信や、喫煙対策プログラム構築、保健師の導入支援など産業保健サービスに携わる。
北海道の拠点病院で糖尿病指導医として勤務。
日々の診療から予防医療の重要さを感じ、産業医も開始。産業医、地方労災医員の活動から診察室と職場をつなぐことの重要性を感じ、これまでの知見をまとめ情報発信を行う。
【関連コラム】