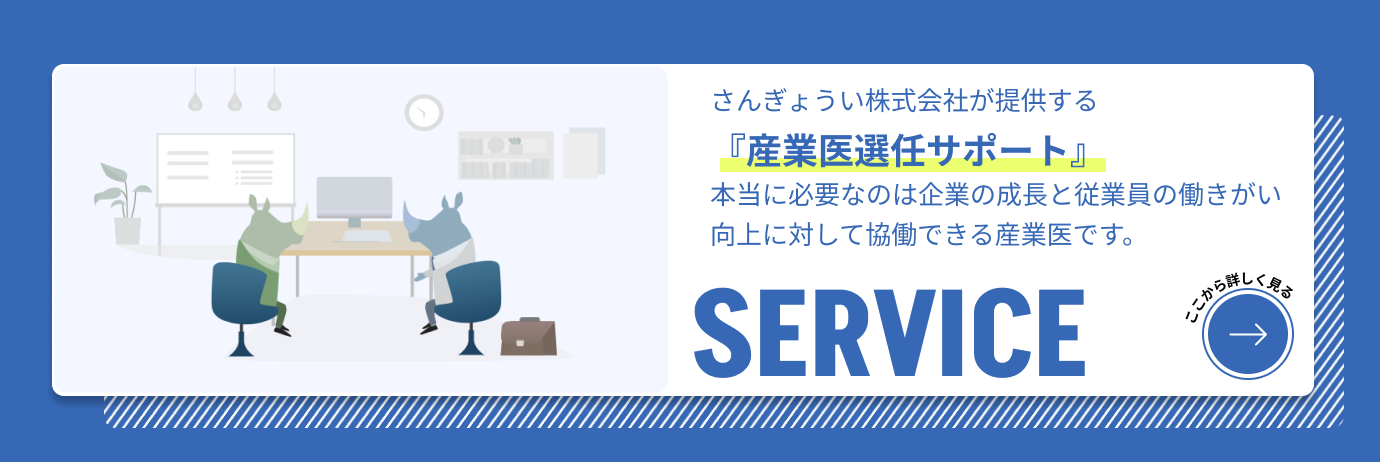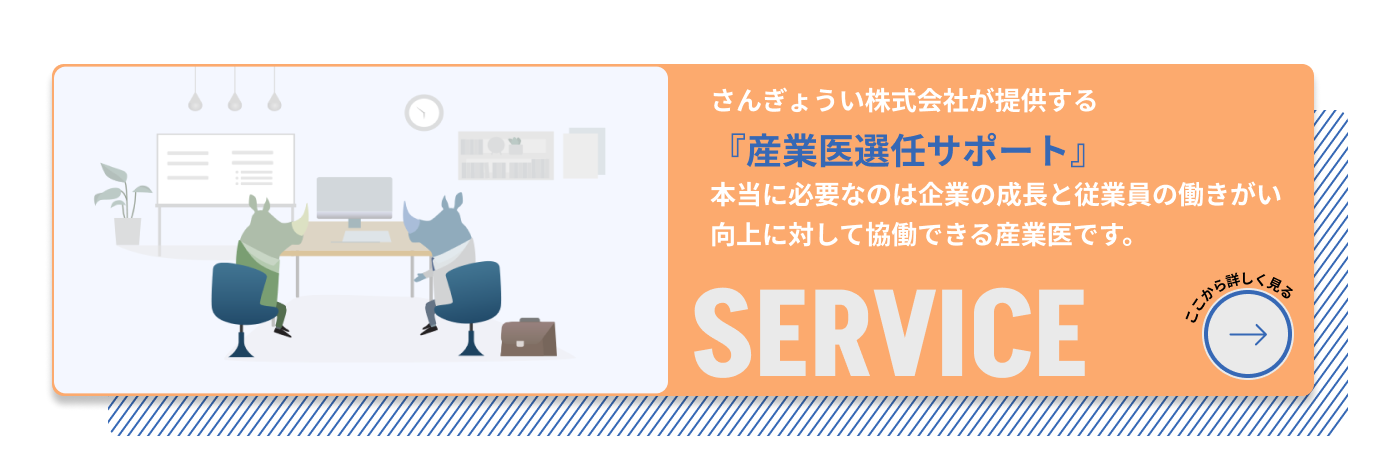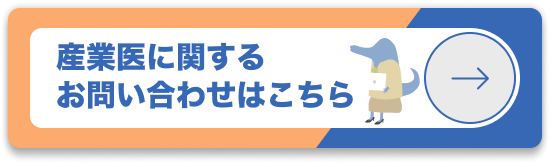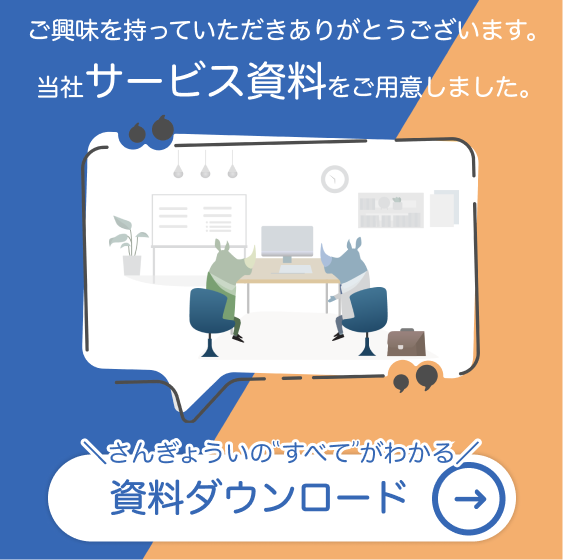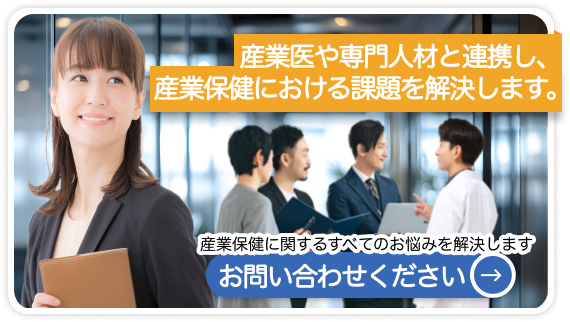【産業保健の視点で解説】長時間労働対策はなぜ必要?中小企業における対策と健康管理の進め方

長時間労働による健康障害は、いまや従業員個人だけでなく企業全体の経営リスクとなりつつあります。心疾患やうつ病などの深刻な健康被害、労災リスク、生産性低下、離職増加などを未然に防ぐには、「労務管理」だけでなく、医学的根拠に基づいた産業保健の視点による対策が不可欠です。
本記事では、厚生労働省のガイドラインに基づいた中小企業向けの「長時間労働対策」について、産業医・保健師の専門性を活用した健康管理体制の構築方法を解説します。
目次
- なぜ「長時間労働対策」が注目されているのか
- 中小企業が長時間労働を放置することの代償
- 産業保健の視点で見る「長時間労働対策」の実践方法
- 中小企業が実践すべき具体的対策
- 専門職の活用で現実的かつ効果的な対策を
- よくある質問(FAQ)
- 持続可能な「健康経営」こそが中小企業の未来を支える
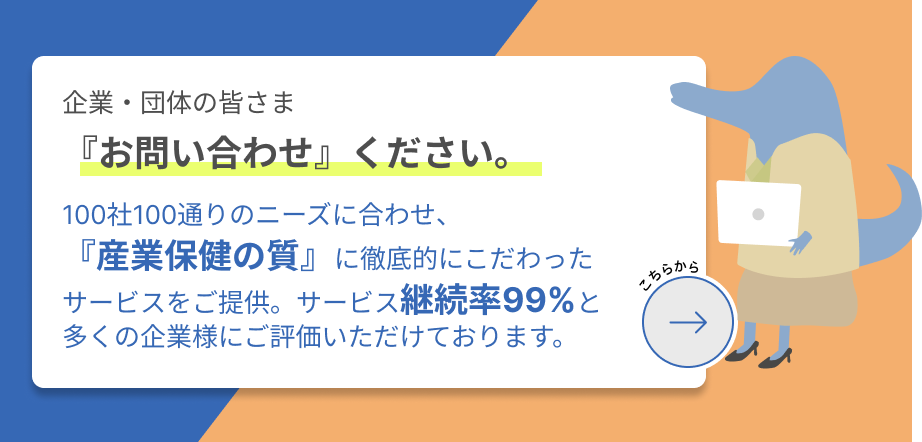
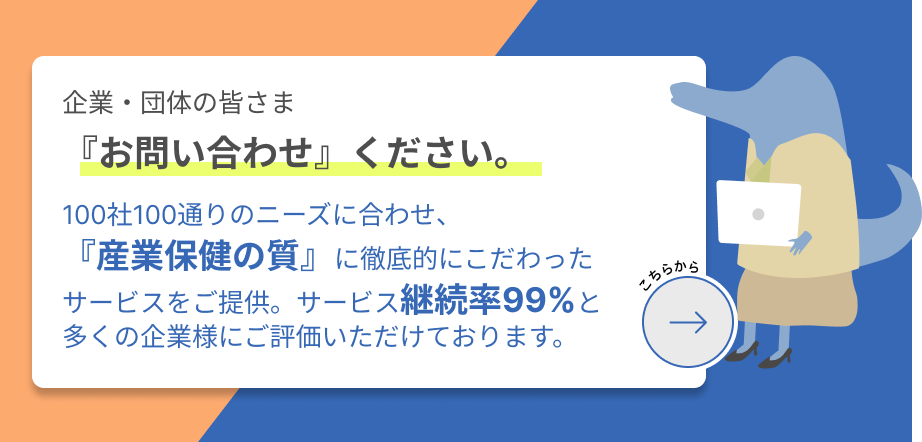
なぜ「長時間労働対策」が注目されているのか
長時間労働がなぜこれほど社会的に問題視されているのか、その背景を把握することは対策を講じるうえで欠かせません。ここでは、健康リスクと社会的動向の両面から、その理由を探ります。
健康障害と労災リスク
長時間労働が続くと、心疾患や脳血管疾患、精神的な不調といった健康障害のリスクが著しく高まるとされています。厚生労働省のガイドラインでは、月45時間超の時間外労働が継続することで健康リスクが増加することが医学的に示されています。
参考:厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署|過重労働による健康障害を防ぐために
法令・社会的背景の変化
法令や社会的背景の変化も、長時間労働対策が注目される要因の一つです。2019年には、働き方改革関連法の施行により、時間外労働の上限が法律で明確に定められ、すべての企業がこれを順守する必要が生じました。さらに、過労死等防止対策推進法の制定によって、企業には従業員の健康に対する配慮義務が強く求められるようになりました。
こうした法的な変化に加え、労働基準監督署による是正勧告や、SNSでの評判拡散といった外部からの視線も強まっており、長時間労働を放置することによる社会的信用の低下リスクが顕在化しています。企業の信頼性やブランド価値を守るためにも、健康管理体制の整備は急務といえるでしょう。
中小企業が長時間労働を放置することの代償
長時間労働を放置することで企業が被るダメージは、健康被害だけにとどまりません。経営面・人材面・社会的信用など、あらゆる側面に悪影響を及ぼす可能性があります。
健康障害による労災認定・訴訟リスクの増加
長時間労働が原因で過労死や自殺などが発生すると、労災認定や損害賠償訴訟に発展する可能性があります。特に中小企業では、一件の事案が経営に致命的な影響を及ぼすことにもつながりかねません。
生産性の低下・人材流出
慢性的な疲労やストレスにより、生産性が低下します。すると、従業員のモチベーションも下がり、離職や採用難に拍車をかける悪循環に陥るリスクがあります。
社会的信用の失墜
労基署からの指導、ブラック企業認定、SNSでの風評拡散などにより、企業ブランドの毀損や取引停止といった深刻な事態につながることもあります。
産業保健の視点で見る「長時間労働対策」の実践方法
中小企業が限られたリソースのなかで無理なく健康管理体制を整えていくには、段階的な導入が効果的です。産業保健の基本である「一次・二次・三次予防」の視点から実践方法を整理します。
健康管理の3段階アプローチ(一次・二次・三次予防)
長時間労働による健康リスクを未然に防ぐためには、予防医学の考え方に基づいた体系的なアプローチが有効です。ここでは、産業保健の基本である一次予防・二次予防・三次予防という3つの段階に分けて、それぞれの対策内容を紹介します。
| 予防段階 | 対策内容 | 主な実施者 |
| 一次予防 | 労働時間管理、職場環境の 調整・改善、健康相談 | 経営者・管理監督者、保健師 |
| 二次予防 | 健康診断、ストレスチェック、面接指導 | 産業医・保健師 |
| 三次予防 | 就業配慮、職場復帰支援 | 産業医・主治医・人事 |
中小企業が実践すべき具体的対策

ここからは、厚生労働省のガイドラインをもとに、中小企業が現実的に取り組みやすい「長時間労働対策」の具体策を紹介します。
厚生労働省が推奨する長時間労働対策
厚生労働省が示すガイドラインをもとに、特に中小企業で実践しやすい対策を以下に整理しました。いずれも法令遵守だけでなく、従業員の健康維持と職場の持続性を支える重要な施策です。
時間外労働の上限(原則月45時間)の厳守
働き方改革関連法により、残業時間の上限は原則として月45時間、年360時間に制限されています。この基準を超える場合は、特別条項付き36協定が必要となりますが、健康リスクの観点からも、可能な限り原則の上限以下に抑える努力が求められます。
労働時間の客観的な記録
タイムカードやPCログ、ICカード等を用いて、実際の労働時間を正確に把握・記録することが推奨されています。紙の自己申告のみでは不十分とされ、是正指導の対象になることもあります。
年次有給休暇の取得促進
2019年からは、年5日の有休取得が企業に義務化されました。計画的付与制度などを活用し、取得しやすい職場づくりを進めることが、心身のリフレッシュと労働意欲の向上につながります。
ストレスチェック制度の活用
常時50人以上の事業場では実施が義務化されているストレスチェック。50人未満の企業でも努力義務とされており、導入することで従業員のメンタル不調の早期発見と職場改善が期待できます。
月80時間超の残業者への医師による面接指導
1ヶ月あたりの時間外・休日労働が80時間を超え、従業員から申し出があった場合、医師による面接指導を実施する義務があります。申し出がなくとも、体調に変化がある場合は早めの対応が望まれます。
再発防止策の策定と実行
一度問題が発生した場合は、原因の分析と再発防止策の立案・実施が必須です。産業医・保健師の助言を受けながら、就業環境や業務配分の見直しを行いましょう。
参考:厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署|過重労働による健康障害を防ぐために
健康障害の初期サインを見逃さない
長時間労働の影響は、目に見えない疲労や精神的な不調として現れます。以下のような兆候がある場合、早期の対応が重要です。
心身の不調は、見えにくい形で現れます。早期のサインを見逃さず、適切な対応を取ることが、深刻な健康被害や労災を防ぐ第一歩となります。
なんとなくだるい・よく眠れない
睡眠不足や疲労の蓄積は、心身の機能低下のサイン。放置せずに声をかけましょう。
保健師の健康相談につなぐのもよいでしょう。
血圧が高い・集中できない
血圧上昇や注意力低下は、過労やストレスによる身体的反応である可能性があります。こちらも前述同様、保健師による健康相談が有効です。
イライラする・やる気が出ない
メンタルヘルス不調の初期症状。職場の人間関係や業務負荷も影響しているかもしれません。メンタルヘルスに不調がある場合、すぐに心理士の活用を検討されるかもしれませんが、まずは産業医や保健師の健康相談で医学的知見でどこにつなぐとよいかスクリーニングを行うことも可能です。
上記のような症状は、早期介入で防げる重大リスクの前兆です。産業保健の視点から早めの介入と支援を行うことが、結果的に企業全体の安定につながります。
専門職の活用で現実的かつ効果的な対策を

制度を整えても、運用・実行できなければ意味がありません。中小企業では、法制度や運用に関する知識が不足していたり、担当者の人数が限られていたりと、体制整備が難しい場面もあります。そんなときこそ、外部の専門職の力を借りることが重要です。
産業医・保健師の役割
長時間労働対策を着実に進めるためには、企業内外の専門職の役割を明確にし、適切に活用していくことが欠かせません。ここでは、産業医と保健師それぞれの担う役割と実務内容について、具体的に紹介します。
産業医
医学的見地から、就業の可否や健康配慮が必要な従業員の評価、面接指導、事業者への意見書提出などを行います。法定義務だけでなく、予防・対応の専門家として活用することが重要です。
保健師
従業員の健康相談や生活習慣の改善指導、ストレスチェック後のフォローアップ、職場環境へのフィードバックなどを担います。日常的な健康支援の窓口として、産業医との連携による相乗効果が期待されます。
弊社のサポート体制(例)
産業保健の体制構築には、自社内の努力だけでなく、外部のリソースや専門家の活用が効果的です。従業員が50名以上いる事業場には法令義務がありますが、それより少ない事業場でも積極的に産業医や保健師を活用し、体制構築を進めるとよいでしょう。
ここでは、中小企業のニーズに応じて柔軟に対応可能な、弊社の代表的なサポートメニューをご紹介します。
【経験豊富な産業医・保健師をスポットまたは定期派遣】
必要なタイミング・頻度に応じて柔軟に対応可能です。
【健康診断・ストレスチェック後のフォローアップ支援】
検査結果の分析や高ストレス者への面接指導なども対応します。単なる実施だけで終わらない体制づくりを支援します。
【地域産業保健センターとの連携によるコスト軽減策】
地域産業保健センターを活用することで、面接指導や健康相談などの支援を無料で受けられる場合があります。弊社では、こうした制度の活用方法についてもアドバイスを行っており、費用面で不安のある企業様にも最適な対応策をご提案可能です。
よくある質問(FAQ)
産業保健体制や長時間労働対策の導入を検討する際に、企業の担当者から実際によく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。導入前の不安解消や比較検討の参考にご活用ください。
Q1. 産業医の選任義務はありますか?
常時50人以上の事業場に義務がありますが、50人未満でも地域産業保健センターで無料支援が受けられます。
Q2. 面接指導はどんなときに必要ですか?
月80時間超の残業と休日労働をした従業員から申出があった場合、医師による面接指導が義務化されています。
Q3. 健康管理にはどのくらいコストがかかりますか?
段階的導入と無料リソースの活用により、最小限の負担での導入が可能です。弊社では、課題の整理や進めていきたい健康管理について、体制構築支援のお手伝いを「伴走型サービス」としてご提供も可能です。ご相談ください。
持続可能な「健康経営」こそが中小企業の未来を支える

長時間労働の放置は、健康障害だけでなく、企業経営全体の危機に直結します。しかし、産業保健の専門性を活用することで、科学的に裏付けされた健康管理体制を無理なく導入することが可能です。 まずは「現状の可視化」から。そして「専門家との連携」によって、御社の健康経営を一歩ずつ、確実に実現していきましょう。
看護師の後、働く人の健康管理に携わるため保健師として産業保健業務に従事する。
現職では、さまざまな規模の企業に対して、個別支援を中心としたかかわりから、広く集団に向けて健康情報の発信や、喫煙対策プログラム構築、保健師の導入支援など産業保健サービスに携わる。