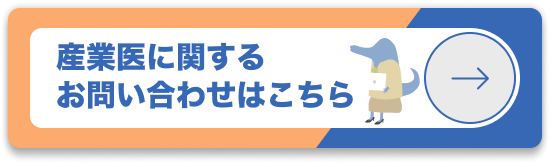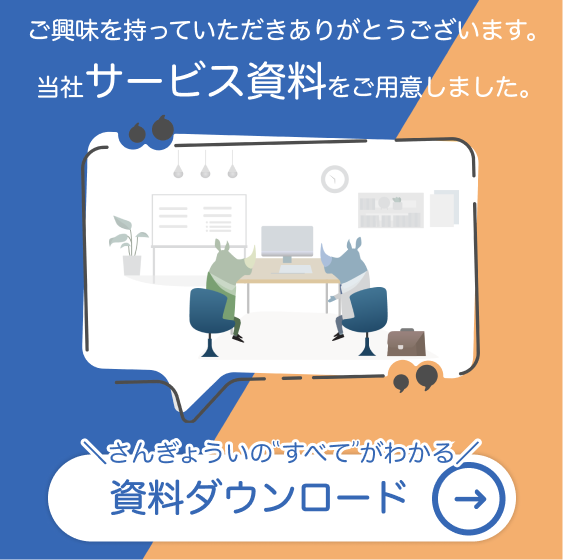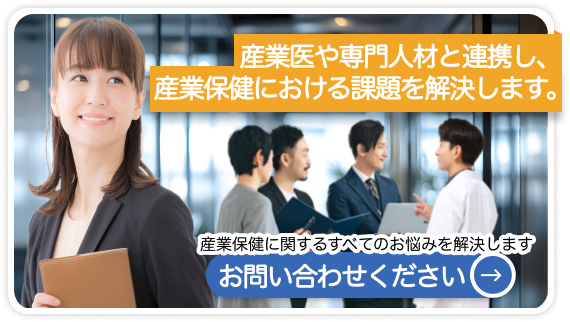研修事例紹介:2025年法改正に対応した熱中症対策の実践

目次
詳細はご参加くださった皆様の感想付きで記載されたこちらの企業ページ(日鉄物産システム建築(株)のnote)をご参照くださいませ。
2025年熱中症ガイドラインをもとに、【日鉄物産システム建築株式会社】にて座学とロールプレイングを併せた研修を行いました。こちらは建設系事業場をお持ちとのことでしたので、現場で起きたことを想定し、まずは本社の皆さんに体験いただきました。

座学を終えていざ、やってみると発見者は自分が何とかしなきゃと一生懸命です。
一つ一つ解説を加えながら、対応のポイントをお伝えしました。
また、救急バックを用意されていても、実際に中身を開いて使うところまで想定して周知している企業は少ないのではないでしょうか。ぜひ、実際に使ってみて、何をどのように使えばいいのか皆さんで確認してみてください。

働く皆様へ:知っておきたい熱中症対策と法改正のポイント
2025年6月1日より、労働安全衛生規則の改正省令が施行され、職場における熱中症対策が罰則付きで義務化されました。これは、特定の条件下の作業に適用されます。具体的には、WBGT(湿球黒球温度)28℃以上または気温31℃以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間を超えて行われる作業が対象です。
事業者に求められる主な対策は以下の通りです。
- 報告体制の整備と周知:熱中症の自覚症状がある作業者や、熱中症の恐れがある作業者を発見した者が、その旨を報告するための体制を事業場ごとに定め、関係作業者に周知することが義務付けられました。緊急連絡網の作成や、職場巡視、バディ制、ウェアラブルデバイス活用など、早期発見に繋がる取り組みが推奨されます。
- 重篤化防止措置の実施手順の作成と周知:熱中症の重篤化を防止するための措置(作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察や処置など)の内容と実施手順をあらかじめ定め、関係者へ周知する必要があります。
- 作業環境の管理と労働者への教育:WBGT値の定期的な測定による作業環境の確認、そして従業員への熱中症リスクと予防対策に関する教育も求められます。
<実際にどうする?具体的な熱中症対策>
フローを作成するだけでなく、日々の現場で実践できる具体的な対策が重要です。
1:体調チェックと「暑熱順化」
- 前日の確認:十分な睡眠をとり、飲酒は控えめにしましょう。熱中症警戒アラートの確認も忘れずに。
- 仕事前の確認:朝食をしっかり摂り、体調が良いかを確認します。体調不良時は無理せず管理者に申し出ましょう。
- 暑熱順化:暑さに徐々に体を慣らす「暑熱順化」は非常に重要です。2週間ほどかけて体を暑さに慣らすことで、体温上昇を抑えられます。
2:適切な水分・塩分補給
- のどが渇いていなくても、こまめに水分と塩分を摂ることが大切です。
- スポーツ飲料や経口補水液を30分ごとにコップ1杯(200ml程度)飲むのが目安です。水分だけでなく塩分も同時に補給しましょう。
3:効果的な休憩と身体冷却
- 休憩時間だけでなく、仕事中もこまめに水分を摂取し、休憩中にできるだけ体を冷やしましょう。
- 休憩サイクルをタイマーで知らせるなど、意識的な休憩を促す工夫も有効です。
- 作業員の様子がおかしいと感じたら、すぐに作業を中断させ、涼しい場所で安静にさせます。意識がない場合や痙攣している場合は、すぐに119番通報し、救急車が到着するまで体を冷やしましょう。服を脱がせ、水をかけて全身を急速に冷却する方法(水かけ冷却)が効果的です。
4:予防対策グッズの活用
- ファン付き作業服、冷却ベスト、ヘルメット用タレなど、熱中症予防グッズを積極的に活用しましょう。
継続的な取り組みで職場を守る
熱中症対策は、一度行ったら終わりではありません。継続的な対策と教育が、従業員の命を守る上で不可欠です。 来年も、皆様の職場での安全と健康をサポートするため、より実践的な熱中症対策研修を企画してまいります。ぜひご参加いただき、一緒に安全で働きやすい職場環境を築いていきましょう。
参考資料
看護師の後、働く人の健康管理に携わるため保健師として産業保健業務に従事する。
現職では、さまざまな規模の企業に対して、個別支援を中心としたかかわりから、広く集団に向けて健康情報の発信や、喫煙対策プログラム構築、保健師の導入支援など産業保健サービスに携わる。