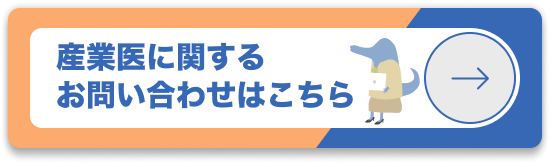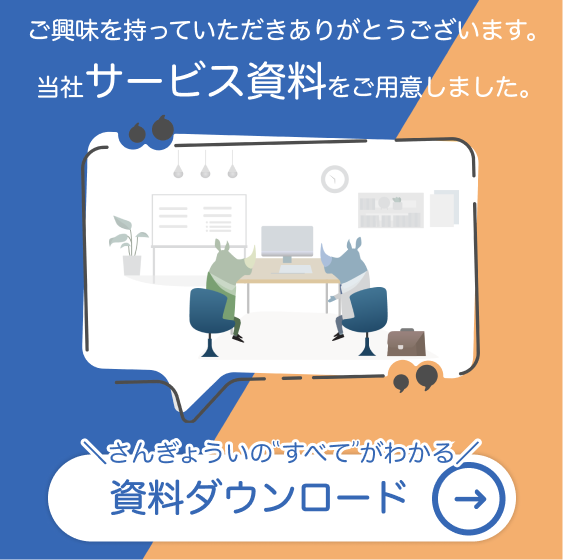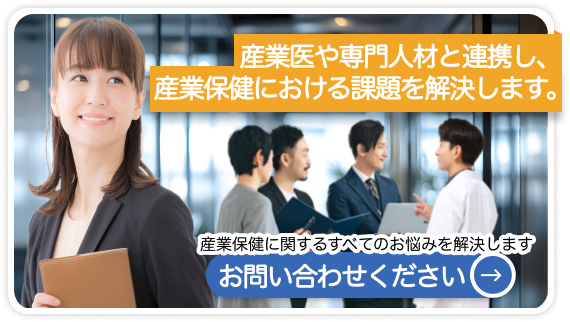第5回:治療と仕事の両立支援|事例紹介 「糖尿病と就業制限」

目次
- 事例:糖尿病を有する労働者の就業制限 ~産業保健スタッフに求められる役割~
- 【解説】1.糖尿病で就業制限を行うのは何のため?
- 【解説】2. 就業制限が必要となる医学的基準はあるか?
- 【解説】3. 糖尿病で就業制限の検討を円滑に進めるための3つのポイント
- 【解説】4. 糖尿病で就業制限をかける前に
- まとめ
事例:糖尿病を有する労働者の就業制限 ~産業保健スタッフに求められる役割~
ある日の朝、〇〇企業専属の産業保健師のAさんは、先週行った定期健康診断の判定内容について、嘱託産業医のB先生から説明を受けている。
B先生:「先週実施した健診の結果をみますと、大部分の方はこのままの勤務を続けてよいですね。ただ、今年も、こちらに記載のあるCさんは、血圧170/100mmHg、HbA1c10%と今年も数値が悪いですね。このまま放置すると心筋梗塞や脳出血などを発症する恐れがあるので、受診を勧めて、治療などができていない状況であれば、残業を控えていただいた方がよいと思います。」
Aさん:「C営業部長ですか…。毎年健診で指摘されおり、私からも受診を勧めているのですが、忙し過ぎて病院に行く時間がないっておっしゃっています。でも産業医が残業は控えた方がってことは、残業禁止ということですか?会社は今、経営的にとても重要な案件を抱えており、C部長がいないと会社が回らなくなってしまうのでは…。」
B先生:「あ、この方は営業部長さんでしたか!社内報にも元気そうな姿が載っていましたね!病院に行く時間を確保してほしいけれど、残業禁止だと、仕事に影響が出てしまうというですね…。体調は良さそうですが、どうしたらいいのでしょうね?私が勤務医として担当している糖尿病患者さんの中にも、結構このくらいの高血糖でも元気に仕事をしている方もいますけどね…。まずは、「医師の意見」を要治療とし、病院に治療をお願いして、仕事が落ち着くまで様子を見ましょうかね?Aさんからも、保健指導お願いできますか?」
そして1週間後、C営業部長は自社のエレベーター内でうずくまっているところを発見され、救急搬送され、心筋梗塞で緊急入院しICUへ…家族は労働災害に相当するではないかと…。
【解説】1.糖尿病で就業制限を行うのは何のため?
労働安全衛生法では、「医師の診断」は健康診断を実施した医師が、糖尿病に関しては血糖値やHbA1cで判定します。異常なし、要精密検査、要治療等です。一方、「医師の意見」は一般には別の医師(産業医、地域産業保健担当医師など)が実施し、仕事のリスクを勘案して、健康診断個人票に記載します。そして「医師の意見」を勘案しながら、事業者が必要な事後措置をすることは法的義務です。健診結果をもとに、従業員が安全・健康に働くことができる健康状態かどうかを確かめ、このまま働き続けても良いかどうかを判断すること(就業判定)が産業医の役割です。今回の事例は、「医師の意見」を述べる時に、糖尿病における就業制限の基準とその進め方に悩んだ話です。産業医が就業制限必要と判断した場合、その目的は大きく3つに分かれます。
その1:仕事による精神的、肉体的ストレスが糖尿病のリスクを悪化させる場合
例えば、従業員が心身に不調をきたしている時や病気がある時に、働き続けることによってその病気が悪化することを防ぐ目的で、就業を制限することがあります。今回の事例のように、仕事が多忙であることを理由に重度の糖尿病を放置している従業員は、睡眠時間の短縮や生活リズムの変動、長時間労働により食事時間が不規則になるため、血糖バランスが崩れる恐れがあります。また、仕事のストレスや疲労の蓄積は心臓や血管へ負荷がかかり、心筋梗塞や脳出血などの病気を発症することがあり、治療により状態が安定するまでの間、暫定的に長時間残業や深夜業務を禁止する必要があります。
夜勤をする場合は長時間労働に加えて食事時間が不規則になるため、血糖バランスが崩れる恐れがあります。そのため、就業制限が必要な人が夜勤をする場合は、休憩時間や勤務間隔の確保が必要です。また、仕事を継続するには主治医や産業医から血糖不良時の対応方法や、内服・インスリン自己注射のタイミングなどの具体的指示を受けて、実行しなければなりません。これらの対処ができない場合、血糖悪化のリスクが高まり就業制限が考慮されます。この措置を講じる際には、詳しい臨床的判断を必要とする場合があり、労働者の同意のうえで、主治医と十分コミュニケーションを取り、情報交換を行うことが求められます。
具体的には以下の仕事では糖尿病による疾病リスクとの兼ね合いで就業制限が考慮されます。
- 遠隔地出張(海外、国内)
- 過重労働
- 高温多湿労働
- 睡眠時間が不規則なシフト勤務(例:夜勤、交替勤務)
- ストレスや時間的プレッシャーが大きい仕事(宅配便、レスキュー)
- 防護服を着用して高温多湿にさらされる仕事
- 救急医療機関から遠い職場での仕事
その2:糖尿病による低血糖、高血糖、合併症が、仕事のリスクを高める場合
糖尿病は慢性合併症を引き起こし、就労の継続や復職に困難を生じます。特に糖尿病性網膜症による視力障害と人工透析に至る糖尿病性腎症は極めて就労糖尿病患者の業務遂行能力に悪影響を及ぼします。糖尿病を有する労働者は他にも多数の潜在的合併症を持っており、それらは仕事上の様々な労働災害を引き起こす可能性があります。例えば、末梢神経障害や起立性低血圧は転倒、転落、骨折など労働事故に繋がり、下肢の閉塞性動脈硬化症は作業中の壊疽、潰瘍を引き起こし敗血症や下肢切断の原因になり、無自覚性低血糖は不慮の交通事故を引き起こし、シックデイによる高血糖は昏睡や意識障害の原因になります。糖尿病は無症候性の心筋虚血が特徴であり、不整脈や心停止により突然死の原因となります。今回の事例では、労働の過重性と未治療の高血圧合併による心血管疾患のハイリスク患者であると判断されますので、医療機関による糖尿病合併症の評価を早期に受けることが必要です。同時に、企業側の安全配慮義務の観点から、面談にて本人に内容を説明し、文書化して記録保存する必要があります。
糖尿病の病型の中でも特に1型糖尿病は、インスリン分泌が高度に枯渇しており、そのため仕事中もインスリン頻回打ちが必須となり、血糖自己測定や自己注射を行う時間と、衛生的かつプライバシーを確保できる環境が必要です。また、インスリンの注射量と炭水化物量をマッチさせる食事療法であるカーボカウントが必要なため、仕事中にも食事時間への配慮が必要です。これらのセルフケアができない場合、高血糖や重症の低血糖のリスクが仕事の安全性に影響し就業制限が考慮されます。一方、2型糖尿病においても、指示された治療を怠り、危険を有する大型の重機などの運転作業を続けると、インスリン注射やインスリン分泌促進系の内服薬により低血糖となり、周囲を巻き込む事故を引き起こす恐れがあります。これらの場合、主治医による就業可能という判定が出るまで就業禁止などの措置をとることがあります。
即ち、糖尿病に併発する疾患とセルフケア能力、そして生理的範囲を超える異常な血糖トレンド(低血糖と高血糖)が、仕事の過重性やリスクを許容できる範囲かどうかが就業制限の鍵になります。
具体的には以下の仕事では糖尿病による疾病リスクとの兼ね合いで就業制限が考慮されます。
- 車両運転作業(パイロット、バス、タクシー、 危険物輸送)
- 落下の危険性のある高所作業(屋根職人、建設作業員)
- 危険な職場(例:消防隊の防護服を付けての消火活動)
- 過圧を伴う仕事(例:潜水士)
- 監視に関わる仕事(例:航空管制官)
- 頻回インスリン療法しながらの不規則労働
- 単独作業、単身赴任
その3:健康管理(保健指導・受診勧奨)のため
長時間残業や交替勤務は、医療機関への受診行動や生活習慣の改善を妨げることがあります。本人自身による医療機関への受診行動や生活習慣の改善を支援する目的で、就業制限や仕事の調整が必要との産業医による意見が出されることがあります。例えば、今回の事例のように糖尿病を放置している従業員に対しては、治療により状態が安定するまでの間、暫定的に長時間残業や休日出勤を禁止する、あるいは、定期受診のための時間を確保するため業務量調整を考慮する必要があります。
【解説】2. 就業制限が必要となる医学的基準はあるか?
数値の基準を一律に決定して就業制限を課すと、個々の従業員の特性によらず、就業制限判断ができます。そのため、血糖値が高い状態による就業中の意識障害や心筋梗塞、あるいは足の壊疽、感染症の発症などによる二次災害のリスクがある社員に対し、受診勧奨を行うことで効率的にリスク軽減につなげることができるかもしれません。従業員の健康と企業のリスクヘッジの最大化を期待して血糖値やHbA1cの数値を参考に就業制限を課す場合があります。しかし就業制限が必要となる血糖値(FBS)やHbA1cの数値に統一的な基準はないことは注意すべき点です。高血糖状態によって引き起こされる疾病リスクが、企業の事業内容や従業員の合併症の状態によって左右されるためです。
近年、リアルタイム持続血糖測定(rt CGM)により、HbA1cだけではわからない予期せぬ血糖トレンドの異常(低血糖・高血糖)を正確に検出し評価できるようになり、就労上のリスク回避の手段として期待されています。特に、血糖変動の激しい1型糖尿病や、血糖調節機構が破綻した二次性糖尿病(膵癌術後、慢性膵炎、肝硬変、ステロイド性高血糖)、厳格なコントロールを求められる妊娠糖尿病の方は、リスクの高い労働をする場合はrt CGMが有用です。
実際に就業制限をつけるかどうかは、血糖値やHbA1cのみではなく、労働者自身の合併症、セルフケア能力、業務のリスク内容、rt CGMによる血糖トレンド(特に低血糖の有無)を総合的に評価して、産業医により判断されます。就業上の措置を検討する可能性がある場合、本人との面接は必須ですが、事業所の規模によっては時間的制約があるので、どのような方に面接をするのか事前に基準を決めておくと効率的です。 以下の面談内容はあくまで一つの目安です。
- 空腹時血糖値200mg/dL以上 あるいは血中ケトン上昇を認め、時間外勤務、出張、夜勤、高所作業、危険作業を行っている方にリスク評価のため面談
- HbA1c8.0%以上で受診勧奨するも受診しない方は、定期受診して一定基準まで改善するまで就業制限を交付するために面談
- 意識障害を伴う無自覚性低血糖を認めた場合、運転業務など危険作業の継続について職務適正を再考するために面談
- 進行性の増殖性網膜症や腎不全、不安定な無症候性心筋虚血、進行性下肢動脈硬化症を認める場合、職務適正を再考するために面談
【解説】3. 糖尿病で就業制限の検討を円滑に進めるための3つのポイント
①産業医に社員情報を提供
産業医が糖尿病での就業制限の内容を考える際には、従業員が普段どんな業務を担当しているのか、どんな働き方をしているのか、職場環境はどうか、インスリン注射や血糖測定する場所が確保されているか、糖尿病による合併症の状態、食事と運動などの生活習慣はどうか、支援者は誰か、服薬のアドヒアランス状況などを、従業員本人との面談を行った上で検討します。従業員が多い場合は限られた時間の中で全ての情報を聞き出すことは難しいので、また本人の話だけでなく、産業保健師や人事労務担当者、衛生管理者から見た状況(勤怠、パフォーマンス、周囲への影響など)も同時に参考にします。面談の際には、産業保健師は、健診結果だけでなく前述した情報を文書で用意し、あらかじめ産業医と共有すると、評価・判断・フォローに役立ちます。
②産業医の意見を書類に残し、共有
面談の結果、産業医が「就業制限が必要」と意見した場合は、必要と判断した理由(どの項目の数値が悪く、このまま働き続けるとどのような影響が考えられるか)、どのような制限が必要かを産業医意見書に記載してもらい、関係者(上司や人事)間で共有できるようにしておきます。就業制限は二通りあり、状況に応じて就業制限をすぐに課す場合と、改善を認めなかった場合は就業制限を課すことを条件に制限を猶予し経過観察とする場合があります。
就業制限の判断や内容は、従業員の状況や担当する業務の内容、職場の体制などに応じていろいろなことを考慮する必要があるため、多様なものとなりがちです。産業医が制限に関する意見を述べる場合、従業員本人や職場の管理者、主治医など、関係者から話を聴き、色々な情報を集めたうえで、総合的に考えて意見が行われることとなります。
就業制限の例として残業(〇時間以上/日)禁止、交代勤務禁止、出張業務禁止、深夜業務禁止、高熱作業禁止、高所作業禁止、単独作業禁止、重筋作業制限・禁止、〇〇取扱い制限があります。
就業制限の必要性の判断が困難な場合は、医療機関の主治医に就業上の意見を求めます。
厚生労働省は、トライアングル型支援として糖尿病のある方が治療と仕事を両立できるよう支援する企業向けガイドライン(指針)を公表しました。企業側に対し、本人の同意を得たうえで働き手である患者の情報を医療機関と共有し、勤務時間の配慮など適切な措置をとるよう求めています。具体的には、
(1)患者が自身の業務内容を主治医に伝える。
(2)主治医が業務内容、病状、治療の内容などから判断して、働き続けるうえで望ましい配慮を主治医意見として企業に伝える。
(3)企業は主治医や産業医、患者の意見をふまえて就業上の措置を決定する。 (4)以上の(1)-(3)をPDCAサイクルで展開する、という流れになります。
産業医の意見で就業制限を行うかを決めるのは会社の責任となりますが、産業医の意見を無視して制限を行わない場合はそれなりの根拠が必要となります。意見書の内容について、不明な点を尋ねて説明してもらう、会社の事情をきちんと伝えるなど、産業医と十分なコミュニケーションを図る必要があります。
③制限の解除を初めから考えておく:Think from the beginning!
就業制限をかける時には、これを解除する時を同時に考えておくことが重要です。例えばHbA1cの数値が悪く残業禁止の制限をかけた場合、治療により数値が改善したのに制限を解除せず残業禁止の状態が続いてしまうと、従業員の働く機会を奪ってしまいかねません。
制限中はどの程度の間隔で面談を行い、定期通院状況を確認するのか、治療により血糖値やHbA1cの数値がどの程度まで良くなったら、あるいは体調がどの程度まで改善したら制限を解除するのか、見通しを産業医に示してもらい、意見書に具体的な就業制限の指示を書類に残し、共有することが大切です。かけっぱなしにしないことが大切です。
①~③の流れについては、過重労働面談による就業制限の流れと概ね類似しておりますので参考になります。
【解説】4. 糖尿病で就業制限をかける前に
個人に最適化した就業制限の措置は、同時に周囲の同僚の負担が増えることになりかねず、公平性の観点からも、職場の健全性を損なう可能性があります。そのため、産業医としては就業制限にはどうしても慎重になるのが実際です。また、仕事を制限することによって本人自身の働く機会や働く意欲を奪い、収入が変わり従業員の生活に影響することもあります。しかし一方では、糖尿病の合併症が出た場合、より大きな経済的負担となることも十分に説明する必要があります。本人と産業保健スタッフとの信頼関係が構築されている場合は、医療機関で実施された血液検査の結果を毎回、産業保健スタッフに提出してもらうことで、定期受診の確認とともに血糖コントロールの推移、併発疾患の状況を把握することもできます。
最近は糖尿病合併症ばかりでなく、癌、感染症などの疾病を抱えた高齢の糖尿病の労働者が多く、これらは労働災害増加の潜在要因となっています。従って確かに会社が安全配慮義務を守るために就業制限をかけることは重要です。しかし、制限をかける前に早期治療を受け、再び健康な状態で働いてもらうことがより望ましいことです。まずは就業制限を考慮するほど疾病リスクが顕在化する前に、早急に医療機関に受診をするように促すことです。今回の事例のように受診勧奨に従わない場合、あるいは疾病リスクが改善していない場合は、産業医面談を設定してそのリスクを説明する必要があります。そして本人は業務内容や労働の過重性を主治医に伝え、主治医意見書を作成していただき、産業医に伝え、納得の上で就業制限をすることが求められます。
このように、糖尿病のある労働者について、産業医面談の設定、外部医療機関と連携、就業制限後のフォローなどが求められますが、多くの従業員を対象とする企業内で、スキルも様々な産業医が単独でこれらを行うことは事実上困難であり、産業保健師や衛生管理者、人事担当者などとの連携が求められます。特に産業保健師は、より身近に健康相談の窓口として従業員に寄り添う存在であり、メンタルヘルスや健康保持増進のスペシャリストとして、産業医と従業員の間に立ちながら両者のコミュニケーションを円滑にする存在として期待されます。産業医が医学的な観点から就業の可否や就業上の配慮事項を判断し、産業保健師が細かなフォローアップを行うことで、スムーズに就労の継続も可能になるといえます。糖尿病における就業制限において産業医と保健師両者の連携は重要です。

まとめ
糖尿病を抱える社員への支援は、産業保健スタッフの重要な役割の一つであり、職場全体での理解と協力が不可欠です。今後は、医療技術や勤務環境の変化に対応しながら、個々の社員が安心して働ける環境を整備し、治療と仕事の両立を支援することが求められます。糖尿病患者の健康を守る取り組みは、社員一人ひとりの幸福度の向上だけでなく、職場全体の生産性向上や企業の持続可能性にも寄与する重要な施策と言えるでしょう。
参考文献
1)厚生労働省:事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン. 2016年
2)Nagata T, et al: Response and Support for Workers with Diabetes: Role of Occupational Health Staff. IIOMT, 68: 255-261. 2020
3)Brod M, et al: The impact of non-severe hypoglycemic events on work productivity and diabetes management. Value Health 14: 665-671, 2011
看護師の後、働く人の健康管理に携わるため保健師として産業保健業務に従事する。
現職では、さまざまな規模の企業に対して、個別支援を中心としたかかわりから、広く集団に向けて健康情報の発信や、喫煙対策プログラム構築、保健師の導入支援など産業保健サービスに携わる。
北海道の拠点病院で糖尿病指導医として勤務。
日々の診療から予防医療の重要さを感じ、産業医も開始。産業医、地方労災医員の活動から診察室と職場をつなぐことの重要性を感じ、これまでの知見をまとめ情報発信を行う。
【関連コラム】