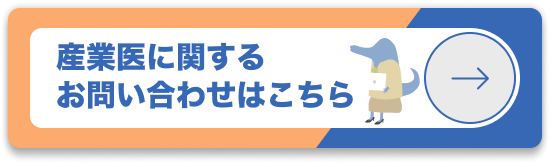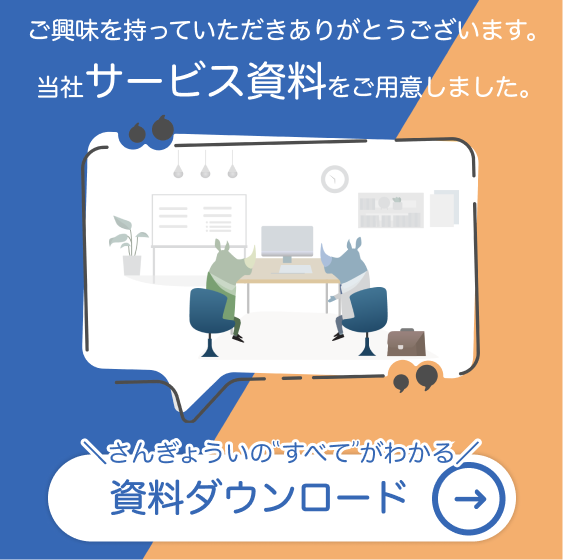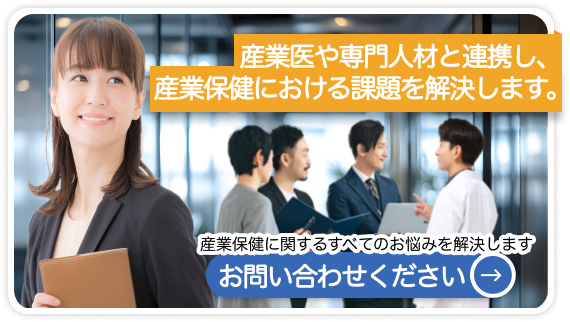新しい衛生委員会づくりと活性化のためにコーディネーターが果たす役割

「自社の衛生委員会は、このままでよいのだろうか?」――もしかしたら、読者の皆さまも、同じような課題をお持ちかもしれませんね。近年の社会情勢や働き方の変化に伴い、衛生委員会の役割は、その重要性を一層増しています。「自社の衛生委員会は、このままでよいのだろうか?」という問いは、まさに現代の企業が直面する本質的な課題を突いた問題意識と言えるでしょう。
さんぎょうい株式会社では、この高まるニーズに応えるべく、『コーディネーター』と呼ばれる存在が、企業の皆さまを力強く支援しています。
本記事では、衛生委員会の基本的な知識から、企業価値を高める委員会づくりのポイント、そして、皆さまの衛生委員会を活性化し、より価値あるものへと変革を導く『コーディネーター』の役割・機能について、詳しくご紹介します。
目次
衛生委員会の基本的な知識とその課題
衛生委員会は、労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場に設置が義務付けられている、企業にとって非常に重要な仕組みです。その根底にある目的は、従業員の皆さまの健康と安全を守り、ひいては職場環境をより良くし、安全と健康に関する文化をしっかりと根付かせることにあります。
労働安全衛生法では、以下の3点が義務付けられています。
- 月1回以上の定期的な委員会開催
- 委員会内容の議事録等を通じた労働者への周知
- 議事録の最低三年間の保管
衛生委員会の主な構成メンバーは、それぞれの役割を担う大切なメンバーです:
| 役割 | 具体的な業務 | |
| 1.委員長 (総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者) | 会議の最終決定権を持ち、事業者へ提言する。 | ・衛生委員会の方針や方向性を示す ・重要な決定事項を承認し、実行を後押しする ・会社全体の安全衛生管理をリードする |
| 2.産業医 | 医学的な観点から指導・助言を行い、従業員の健康管理を支援する | ・健康診断の結果や職場環境のリスクについて意見を述べる ・ストレスチェックやメンタルヘルス対策を提案する ・労働環境の改善に関する医学的アドバイスを行う |
| 3.衛生管理者 | 労働安全衛生法に基づき、職場の衛生管理を担当する | ・職場の衛生状態をチェックし、必要な改善策を提案する ・労働者の健康リスクを把握し、適切な対策を講じる ・衛生委員会での議論を実務に落とし込む |
| 4.労働者代表 | 現場の声を反映し、従業員の立場から意見を述べる | ・実際に働く環境で感じている問題点を提起する ・改善案や現場の要望を委員会に伝える ・他の従業員と情報を共有し、意識向上に貢献する |
※参考:厚生労働省|安全委員会、衛生委員会について教えてください。
なお、人数について法令上の定めはありませんが、事業者側と労働者側をそれぞれ半数ずつ指名するのが基本です。安全委員会と衛生委員会は、業種の指定の有無などで違いがありますが、両方の設置義務がある場合は「安全衛生委員会」として統合して設置することもできます。
しかしながら、多くの企業では衛生委員会が形骸化し、本来の目的を果たせていないという課題を抱えています。その理由として、法令遵守(月1回の開催)が目的化してしまっていること、構成メンバーが目的を理解していないことなどが挙げられます。
また、決まりきった議題しか話されず、報告会と化しているケースも多く見られます。これは、衛生委員会が「報告を受ける場=トップダウンの場」であるという従来の捉え方と、現在のニーズとの間にズレが生じていることが根本的な原因となっていると考えられます。
このような社会や職場環境の変化を背景に、多くの企業が衛生委員会の運営や活用方法について課題を抱えている状況が見受けられます。
企業価値を高める衛生委員会づくりのポイント
現代において、衛生委員会はもはや単なる法令遵守の場ではありません。むしろ、企業がリスクを未然に防ぎ、従業員にとって安全かつ快適な職場環境を作るための、重要な機能を担う場として位置づけるべき時代が来ています。
従来の従業員一人ひとりの健康・安全を守るといった、いわば福利厚生的な産業保健の枠を超え、「集団全体に対する健康管理」という視点を持つことが、今、非常に重要です。なぜなら、労働安全衛生の環境が悪化すれば、例えばインフルエンザの集団感染で製造ラインが停止するなど、企業の経営リスクにつながる可能性があるからです。
企業価値を高める衛生委員会を実現するためには、以下の4つのポイントが重要です。
- 「ボトムアップの場」としての認識の統一と実践
- 企業活動との連携
- PDCAサイクルの導入
- 外部情報や事例の活用
「ボトムアップの場」としての認識の統一と実践
衛生委員会が単なる報告会ではなく、現場の声を吸い上げ、会社を良くする施策を打ち出すためのボトムアップの場であるという認識をメンバー全員で共有し、実践していくことが不可欠です。
集団に対する健康管理へのシフト
従業員個人の健康だけでなく、企業全体の健康リスクを管理し、予防・改善を図る「集団に対する健康管理」の視点を取り入れることで、経営リスクの低減と企業活動の安定化を目指します。
企業活動との連携
健康診断やストレスチェックの時期、繁忙期などを考慮した議題の年間スケジュールを作成し、企業活動と委員会の運営を連携させることで、会議をより具体化・活性化させます。これにより、従業員の健康状態を可視化することで、経営リスクを適切に管理できます。
PDCAサイクルの導入
計画・実行・評価・改善(PDCA)のサイクルを継続的に回すことで、施策の効果測定を行い、成果を積み上げます。これにより、委員会メンバーの意識や企業内の衛生委員会に対する認識が確実に変化し、企業文化として定着していきます。
外部情報や事例の活用
「新しい衛生委員会」を実現するための一つの有効な解決策として、外部のコミュニティーや他社事例、公的機関の情報等を取り入れることが有効です。
コーディネーターの役割・機能

さて、さんぎょうい株式会社が考える、企業価値を高める衛生委員会づくりを皆さまと共に実現していくための大切な存在が、『コーディネーター』です。コーディネーターは、まさにその名の通り「調整役」として、多岐にわたる役割と機能を果たし、皆さまの取り組みを力強く支えます。
コーディネーターが企業や産業医に対して働きかける際の具体的な役割・機能を、以下にてご紹介いたします。
企業に対するコーディネーターの働きかけ
【スタート時における目的意識の統一】
衛生委員会の新規立ち上げ時やメンバー交代時に、「職場環境の改善と安全及び健康に関する文化の定着」という本来の目的意識を、メンバー全員で共有・統一することを支援します。
時には「会社を良くする施策を打ち出せるボトムアップの場なのに、活用しないのは勿体ないですよ」といった具体的な言葉で、メンバーの意識に寄り添いながら説明を行うこともあります。
【組織を動かすための要件のアドバイス】
委員会活性化の前提となるメンバーのアサイン、時間確保、予算措置といった組織運営の必須条件について、必要に応じてアドバイスし、委員会運営者側を裏方としてアシストします。
【委員会議題の年間スケジュール作成】
健康診断やストレスチェックの時期、繁忙期・長時間労働が発生する時期などを明確にし、年間スケジュールに落とし込むことで、企業活動と連携した具体的な議論を促します。
【委員会運営へのPDCAサイクル導入】
月次労働時間データなどの分析や、今年度との比較、施策の効果測定など、PDCAサイクルを継続的に回すことで、委員会の成果を積み上げ、メンバーの意識や企業内の衛生委員会に対する認識が確実に変化し、定着するようサポートします。
衛生委員会開催時の3つの実践ポイント
1.積極的な情報提供
企業の産業保健に関連する法改正の動向や、他社事例(同業・異業種の先進事例など)を積極的に提供します。また、労働基準監督署からの評価視点など、多角的な情報提供を心がけています。
2.企業活動と連動した年間スケジュール作成やPDCAサイクル導入のフォローアップ
委員会運営を徹底的にフォローし、会議を実行ベースに乗せることで、担当者の負担軽減にもつながります。コーディネーターはあくまでアドバイザー的な立場ですが、方向性の示唆や軌道修正などを、委員会の運営者と積極的に擦り合わせを重ねてまいります。
3.コミュニケーション活性化のためのファシリテーション
オープンクエスチョンを投げかけるなど、参加者を巻き込むファシリテーションを行い、活発な議論を促します。新メンバーがいらっしゃる期初には、一通りの自己紹介だけでなく、お人柄がわかるような工夫を凝らすこともあります。
産業医に対するコーディネーターの働きかけ
【産業医との連携強化】
「産業医と衛生委員会の連携が難しい」という課題を抱えている企業は少なくありません。衛生委員会を活性化するには、産業医と企業とのコミュニケーションも重要な要素です。コーディネーターは、産業医にしかできない仕事に集中してもらうためにも、企業と産業医の架け橋となるよう努めます。
【衛生講話テーマのアドバイス】
産業医に対して、健康診断の時期に合わせた講話テーマの提案など、企業活動とリンクした内容にするようアドバイスします。
【産業医への情報提供】
ストレスチェックの分析結果、企業の特性、これまでの活動経緯、同業・異業種の他社動向など、過不足のない情報を共有することで、企業が求めるものと産業医の対応とのミスマッチ解消を目指します。
実際に、コーディネーターとの協働によって、インフルエンザ予防接種の費用補助が実現した事例があります。コーディネーターがBCP(事業継続計画)の観点から予防接種補助の有益性をアドバイスしたことで、従業員の健康維持が企業活動の滞りない推進につながるという判断がなされ、会社の意思決定に影響を与えました。これはまさに「集団に対する健康管理」という新しい産業保健への対応例であり、企業価値を高める産業保健の実現に向けた衛生委員会のリード役としての役割を示しています。
コーディネーターは、企業の実情やニーズを深く理解し、「企業に寄り添う姿勢」を出発点として調整役を担います。産業医との信頼関係構築を重視し、安易な産業医交代ではなく、適切な情報提供と調整によってミスマッチを解消することを目指します。
まとめ:付加価値の高い衛生委員会の実現に向けて
コーディネーターとの協働が、衛生委員会を活性化するヒントになります。
経験豊富なコーディネーターは、労働安全衛生活動を企業文化・風土醸成の取り組みのひとつと考えております。なぜなら、百の企業があれば、百通りの企業文化や風土があるように、衛生委員会をより良くしていくための最適なプロセスもまた、それぞれに異なるからです。
さんぎょうい株式会社のコーディネーターは、皆さまの企業が新たな産業保健の土壌を育むための心強い伴走者として、企業が目指す方向性を深く理解し、産業医をはじめとする関係者の意思疎通を図ります。
さらに、日々産業保健の新しい情報に触れ、複数の他社事例を持つ私たちだからこそ、社内ではなかなか発言しづらいような内容にも、一歩踏み込んで意見を述べられるというメリットもきっと感じていただけるはずです。
私たちさんぎょうい株式会社は、企業の成長と、そこで働く皆さまの働きがいが両立する未来を支援することをミッションとして活動しています。コーディネーターは、企業の皆さまの実情や課題に寄り添い、委員会メンバーの方々と協働しながら、企業のリスクヘッジや、従業員が働きやすい環境づくりに寄与する衛生委員会を作り上げていくお手伝いをいたします。
ぜひ、さんぎょうい株式会社のコーディネーターにご相談ください。皆さまとの出会いを心よりお待ちしております。