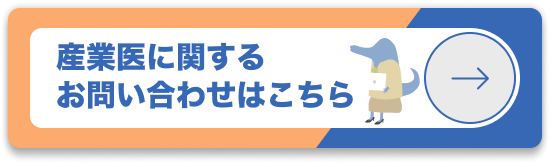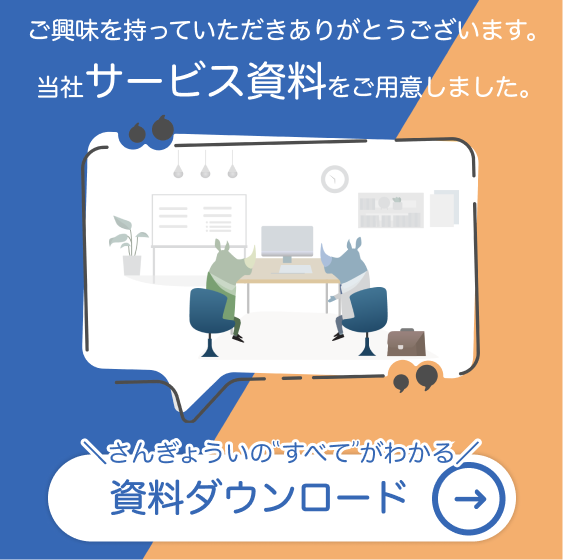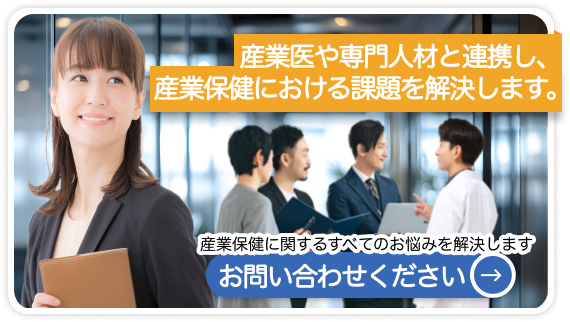第4回:職場における糖尿病対策~連携・情報共有・緊急対応~

目次
1.情報共有と連携
職場における糖尿病患者の支援体制構築には、医療機関との連携および情報共有が欠かせません。まず、医療機関との連携を強化する必要性について解説し、次に情報共有の方法と効果について述べます。
1-1 医療機関との連携強化の必要性
糖尿病は、食事、運動、薬物療法と多岐にわたる自己管理が必要な生活習慣病ですが、急性、慢性合併症によるQOLの低下、高齢化による併存症の増加、社会的不利益や差別が問題となっています。最近、医療技術の進歩と相まって少子高齢化と労働力不足の中、働きながら治療を継続していくことが求められています。こういった厳しい状況の中で企業の安全配慮義務を果たすためには、仕事と病気のそれぞれのリスクを理解しながら両立支援するという、職場全体の理解と適切な配慮が一層不可欠となっています。一方、企業側が個々の従業員の病状や治療内容を詳細に把握することは容易ではありません。
そこで、医療機関との連携が重要になります。主治医は患者の病状、治療方針、日常生活における注意点などを熟知していますが、仕事に関する情報が十分ではありません。企業は仕事に関する情報はありますが、疾病に関する情報が不足しています。企業と主治医がそれぞれの情報を補い合いながら、それぞれのリスクを共有することで初めて適切な就労環境整備や治療継続支援が可能となります。
具体的には、企業と主治医との情報交換を通して、以下の事項を把握することが重要です。
- 現病歴、既往歴、慢性合併症の病期、自覚症状の有無、身体所見、治療方針
- 服薬状況、インスリンの有無、血糖コントロール状況、その他の検査データ
- 日常生活における注意点(食事、運動、服薬、血糖測定など)
- 低血糖や高血糖時の緊急時の対応方法、自己血糖測定の有無
- 就業上の配慮事項(勤務時間、休憩時間、作業内容など)、雇用状況
- 産業保健スタッフの有無、支援する職場の緊急連絡先
- 定期的な通院の必要性(診療科の確認)
これらの情報を適切に共有することで、企業側は従業員の病状に応じた就労上の配慮を適切に行うことができます。例えば、低血糖時の対応策を主治医に事前に相談し、職場内で共有しておけば、緊急時にも迅速かつ適切な対応が可能になります。また、定期的な通院の必要性を職場スタッフが理解していれば、通院のための休暇取得にも柔軟に対応できます。
1-2 情報共有の方法とその効果
企業で働く中で、就労と糖尿病治療の両立に困難や問題がある場合、医療機関との情報共有は、適切な方法で行うことが重要です。厚労省の両立支援ガイドラインを参考に述べます。まず、従業員から主治医に企業情報や健康上の問題点を提供します。そこで、主治医は従業員の疾病の状態と就労上のリスクを総合的に勘案して、主治医意見を作成し企業に提出します。企業は主治医意見をもとに、職場を熟知している産業医や産業保健スタッフと相談の上、最終的に就労上の措置を決めます。この場合、プライバシー保護の観点から、従業員の同意なく情報を共有することはできません。従業員から同意を得た上で、書面や電話、オンラインシステムなどを利用して情報共有を行います。
従業員の主治医、産業医、企業との情報共有には、以下の手順があります。
- 従業員が主治医に情報提供を依頼する。
- 産業医が従業員の同意のもとで主治医に情報提供を依頼する。
- 従業員が産業医に情報提供を行い、産業医が主治医に伝える。
- 主治医は就労と治療の両立に必要な情報を、従業員の同意のもとに企業に提供し、産業医や産業保健スタッフの意見のもとに就労上の措置を決定する。
情報共有をスムーズに行うためには、職場における糖尿病患者支援のための書式を活用する方法もあります。例えば主治医に「糖尿病患者就労状況報告書」の作成を主治医に記入してもらうことで、必要な診療情報を効率的に収集できます。また、職場は「職業情報収集票」を作成し、主治医に渡すことで職場環境や業務内容を具体的に伝えることができます。
情報提供書については以下の参考書式が出されておりダウンロードできます。
- 事業所における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン 厚生労働省
- 就労と糖尿病治療の両立支援手帳 独立行政法人 労働者健康安全機構
医療機関との情報共有を適切に行い、治療と仕事の両立支援を行うことで、以下のような効果が期待できます。
- 従業員の病状に応じた適切な就労環境の整備
- 治療継続の支援と重症化予防
- 緊急時の迅速かつ適切な対応
- 職場における糖尿病への理解促進
- 従業員と企業間の信頼関係構築(会社への感謝、誠意、やる気の向上)
- 能力と意欲のある多様な人材を確保し離職、中断を回避
情報共有は、職場における糖尿病患者支援において非常に重要な役割を果たします。関係者間で積極的に情報共有を図り、より良い職場環境づくりを目指しましょう。
2.緊急時対応策:職場での糖尿病サポート

糖尿病を持つ従業員にとって、職場は生活の大部分を占める大切な場所です。しかし、日常生活に溶け込んでいるからこそ、緊急事態が発生した際に適切な対応が求められます。特に、低血糖とシックデイは、迅速かつ的確な処置が必要となるため、周囲の理解と協力が不可欠です。
2-1 低血糖時の対応方法
低血糖は、血糖値が異常に低下した状態で、主にインスリン製剤の自己注射療法やインスリン分泌刺激系の内服薬を服用している場合に発症します。薬剤による血糖低下作用が、食事量や労働量とのアンバランスが原因で生じます。放置すると意識消失や痙攣などの重篤な症状を引き起こす可能性があるため、迅速な対応が求められます。
低血糖の兆候を見つける
低血糖は、人によって症状が様々です。冷汗、ふるえ、動悸、めまい、倦怠感、意識混濁、空腹感、頭痛、イライラ感など、普段とは異なる様子が見られたら、低血糖を疑いましょう。また、顔が青白くなったり、呂律が回らなくなったりするケースもあります。血糖値の程度によって症状の出現に個人差も大きく、特に、無自覚性低血糖には注意が必要です。長期間の糖尿病歴があり自律神経障害が進行したり、頻回に低血糖を繰り返すことのより低血糖に”慣れて”しまったりした場合に、かなりの低血糖でも自覚症状が出にくくなり、仕事中に突然意識を失い倒れ救急搬送が必要となることがあります。
低血糖時の対応
低血糖の疑いがある場合は、まず血糖値を測定します。70mg/dL未満であれば低血糖と判断し、以下の手順で対応します。血糖測定ができない場合も緊急対応として同様の手順で対応します。
ブドウ糖の摂取
ブドウ糖は、即効性が高く、低血糖時の血糖値を素早く上昇させる効果があります。ブドウ糖の錠剤やゼリー飲料などを用意しておき、10~15gを摂取させます。砂糖でも代用できますが、吸収速度が遅いため、15~20g摂取する必要があります。α-グルコシダーゼ阻害薬を服用している場合は、砂糖ではなくブドウ糖を摂取するようにします。
安静
ブドウ糖を摂取したら、楽な姿勢で安静にさせましょう。15~20分程度で症状が改善することが多いですが、改善しない場合は再度ブドウ糖を摂取します。
①意識障害がある場合
意識が混濁していたり、呼びかけに応じない場合は、重症低血糖の可能性があります。至急救急車を呼び、医療機関へ搬送しましょう。グルカゴンキットが処方されている場合は、使用を検討します。ただし、グルカゴンは、肝臓にグリコーゲンが蓄えられている場合にのみ効果を発揮するため、過度な期待は禁物です。
・意識消失の場合または意識消失の恐れがある場合:
- 救急医に連絡する。
- 患者を安定した横向きの姿勢にする。(窒息の危険があるので、寝かせたら飲食はさせない)
- 口内に食べ物が残っていれば取り除く。
- 固定していない入れ歯は外す。
- グルカゴンを注射する(介護者が慣れている場合)。
- バクスミーでグルカゴンを点鼻投与する(介護者が慣れていない場合)。
- 起きた後にグルコースを与える。
- 低血糖が回復後も意識が回復しなければ、重篤な心、脳血管疾患を疑い医療機関に搬送する。
②回復後の食事
低血糖症状が落ち着いたら、軽食を摂らせましょう。サンドイッチやおにぎりなど、糖質を含む食品が適しています。その後の低血糖再発予防のため、持効性のある糖質の摂取も有効です。
③次回受診時に必ず主治医に報告し、相談する。
職場での注意点
- 従業員に低血糖の症状や対処法を教育し、緊急時の対応を周知徹底しておく。
- 従業員がブドウ糖を常備できるように、職場にブドウ糖を備蓄しておくことが望ましいです。
- 定期的な休憩時間を設け、従業員が無理なく血糖値の管理を行えるように配慮する。
- 低血糖発作を繰り返す従業員には、産業医や主治医との連携を強化し、就労環境の調整を図る。
- 自動車運転など危険を伴う作業に従事している場合は、低血糖時の作業中止を徹底する。特に、運転業務の場合、直ちに停車し糖分の補食後、症状が消失したあとも少なくとも30分以上の時間をおいてからの運転再開が必要。
※2013年に道路交通法が改正され、運転に支障がある症状を自覚しながら、運転免許取得、更新時に申告しなかった場合、罰則が新設されました。
2-2 シックデイ時の対応
シックデイとは、糖尿病患者において、感染症による発熱や消化器症状(嘔吐、下痢)のみならず外傷、歯科治療、ステロイド投与、通院での抗がん剤治療などに加わる身体的ストレスによって、非日常的に血糖コントロールが困難になった状態を指します。糖尿病患者は、感染症にかかりやすく、重症化しやすい傾向があるため、シックデイ時の対応は非常に重要です。
シックデイの兆候を見つける
発熱、咳、鼻水、嘔吐、下痢などの症状が見られたら、シックデイの可能性を疑います。また、食欲不振や倦怠感なども重要なサインです。
シックデイ時の対応
シックデイ時は、高血糖と脱水に注意が必要です。 従業員に主治医から指導されている対応方法を共有してもらい、対処できるように準備しておきます。
①安静
体調が悪い時は、無理せず安静を保つことが大切です。職場では早退や休暇を取得させ、自宅療養を促します。
②水分補給
発熱や嘔吐、下痢などで脱水症状に陥りやすい状態です。こまめな水分補給を促します。経口補水液やスポーツドリンクなどが適しています。
③食事
食欲がなくても、少量ずつでも良いので、炭水化物を含む食事を摂ることが重要です。おかゆ、うどん、スープなどがおすすめです。全く食事が摂れない場合は、主治医に相談することを促します。
④血糖値・ケトン体の測定
可能であれば、こまめに血糖値と尿ケトン体、あるいは血液ケトン体を測定し、血糖コントロールの状態を確認が必要です。高血糖やケトン体陽性が続く場合は、医療機関への受診が必要です。最近はSGLT2阻害薬服用による正常血糖ケトアシドーシスが多くなっており、血糖値が正常であっても注意が必要です。
⑤薬剤調整
服用中の薬によっては、シックデイ時に調整が必要な場合があります。インスリン注射を行っている場合は、指示された量を注射することが大切です。緊急時など必要に応じて経口糖尿病薬の中止やインスリン量の調整が以下のように必要になることがありますが、具体的には主治医に相談するように伝えます。
<具体的対応 >
- スルフォニル尿素薬、速効型インスリン分泌促進薬:インスリンを分泌して血糖値を下げるので、食事量に合わせて加減します。食べられない場合は中止します。
- ビグアナイド薬、SGLT2阻害薬:絶対に中止すべき薬です。
- αグルコシダーゼ阻害、GLP1受容体作動薬:吐気、腹痛など、おなかの症状がある時は中止します。
- インスリン製剤:シックデイで食事が摂れなくても中止してはいけません。全く食が摂れなくても普段の半分程度のインスリンが必要です(特に中間型、持効型インスリン)。食事前に必要なボーラスインスリンは食後打ちに切り替えて食事が摂れない場合は中止します。頻回に血糖測定を行い測定結果に応じて増減するスケール法が一般的ですので、あらかじめ主治医と確認すると良いです。
⑫医療機関への連絡
症状が改善しない場合や、高血糖・ケトン体陽性が続く場合は、速やかに医療機関に連絡し、薬の調整などの指示を仰ぎましょう。重症化を防ぐためには、早期の受診が重要です。
シックデイ時の職場での注意点
- 従業員にシックデイの症状や対処法を教育し、緊急時の対応を周知徹底しておきます。
- 従業員が体調不良を訴えた場合は、速やかに休息を取らせ、無理に仕事をさせないように配慮します。
- 必要に応じて、医療機関への受診を勧奨し、通院のための休暇取得を支援します。
- 産業医や主治医と連携し、従業員の病状に応じた就労上の配慮を行います。
糖尿病は、適切な治療と自己管理によって、健康な生活を送ることが可能な病気です。職場での適切なサポート体制を構築することで、従業員が安心して働き続けられる環境づくりを目指しましょう。
3.支援体制の改善

3-1 職場でのサポート体制の構築と改善策
糖尿病を持つ社員にとって、職場は生活の大部分を占める大切な場所です。だからこそ、安心して仕事に取り組める環境づくりは、会社全体の生産性向上にも繋がります。ここでは、職場における糖尿病社員へのサポート体制の構築と改善策について、具体的な方法を交えながら説明します。
① 理解と共感の風土づくり
何よりも大切なのは、糖尿病という病気を正しく理解し、社員への共感を持つことです。糖尿病は、生活習慣病と言われることもありますが、遺伝や体質、様々な要因が複雑に絡み合って発症します。決して本人の努力不足が原因ではありません。偏見や誤解に基づく言動は、スティグマ(stigma)や社会的不利益、差別に繋がり、社員の精神的な負担を増し、症状悪化に繋がる可能性も懸念されます。
定期的な社内研修や啓発活動、アドボカシー(adovocacy)活動を通して、糖尿病に関する正しい知識を共有し、社員同士が支え合える雰囲気を作りが重要です。
②情報共有と相談しやすい環境
糖尿病の治療は、食事療法、運動療法、薬物療法などを組み合わせ、個々の症状や生活スタイルに合わせて行います。そのため、職場の上司や同僚に病状を伝えることは、適切なサポートを受ける上で非常に重要です。
社員が安心して相談できる窓口を設け、プライバシーに配慮した情報管理体制を整えましょう。産業医や保健師との連携はもちろんのこと、必要に応じて主治医との情報交換を行うことも有効です。
③柔軟な勤務体制の整備
通院や血糖値の変動など、糖尿病を持つ社員は、勤務時間や休憩時間に特別な配慮が必要となる場合があります。
例えば、通院のための時間確保や、低血糖時の休憩場所の提供、休憩時間の柔軟な運用などを検討してみましょう。また、在宅勤務や時短勤務制度の導入も、社員の負担軽減に繋がります。
④緊急時対応マニュアルの作成
低血糖や高血糖など、糖尿病には緊急時対応が必要な場面があります。社員が安心して働けるよう、緊急時対応マニュアルを作成し、社員と共有します。
マニュアルには、緊急時の連絡先、対応方法、必要な備品の保管場所などを記載し、定期的な訓練を実施することで、迅速かつ適切な対応が可能となります。
⑤定期的な面談と健康診断
健康診断による適切な事後措置は労働安全衛生法による法的義務であることを周知しましょう。社員の健康状態を把握し、適切なサポートを提供するために、定期的な面談と健康診断の実施は欠かせません。面談では、仕事上の課題や不安、治療に関する悩みなどを丁寧にヒアリングし、必要に応じて専門家への相談を促します。
また、健康診断の結果を基に、生活習慣改善のアドバイスや治療方針の見直し、社員の健康管理をサポートすることも重要です。
⑥個別対応への配慮
糖尿病は一人ひとりの症状や生活スタイルによって、必要なサポートも異なります。画一的な対応ではなく、個々の状況に合わせた柔軟な対応を心掛けることが大切です。
糖尿病の症状や治療の副作用、合併症による障害の程度によって、業務内容への影響が生じることがあります。治療状況や業務遂行能力も踏まえた就業上の措置が必要となります。重症慢性合併症では、視力障害や血液透析、下肢切断を防ぐため就労場所の変更、労働時間の短縮、深夜業務の制限の必要があります。インスリン自己注射による低血糖は両立支援上大きな問題です。自己のみで対処のできない無自覚性低血糖のある方は、リスクのある運転作業、危険作業は絶対避ける必要があります。
このように、就労措置をきめる場合に、血糖コントロール不良のみで安易に就労禁止するのではなくて、できるだけ配置転換、作業時間短縮など必要な措置を検討し、治療内容や生活習慣、仕事内容などを考慮し、個別のサポートプランを作成することで、より効果的な支援が可能となります。
これらの取り組みを通して、糖尿病を持つ社員が安心して働き続けられる職場環境を構築することは、労働の意欲向上にも繋がり、会社全体の成長にも大きく貢献するはずです。社員一人ひとりの健康と幸せを大切にする企業文化を育んでいきましょう。
看護師の後、働く人の健康管理に携わるため保健師として産業保健業務に従事する。
現職では、さまざまな規模の企業に対して、個別支援を中心としたかかわりから、広く集団に向けて健康情報の発信や、喫煙対策プログラム構築、保健師の導入支援など産業保健サービスに携わる。
北海道の拠点病院で糖尿病指導医として勤務。
日々の診療から予防医療の重要さを感じ、産業医も開始。産業医、地方労災医員の活動から診察室と職場をつなぐことの重要性を感じ、これまでの知見をまとめ情報発信を行う。
【関連コラム】
第5回:治療と仕事の両立支援|事例紹介 「糖尿病と就業制限」