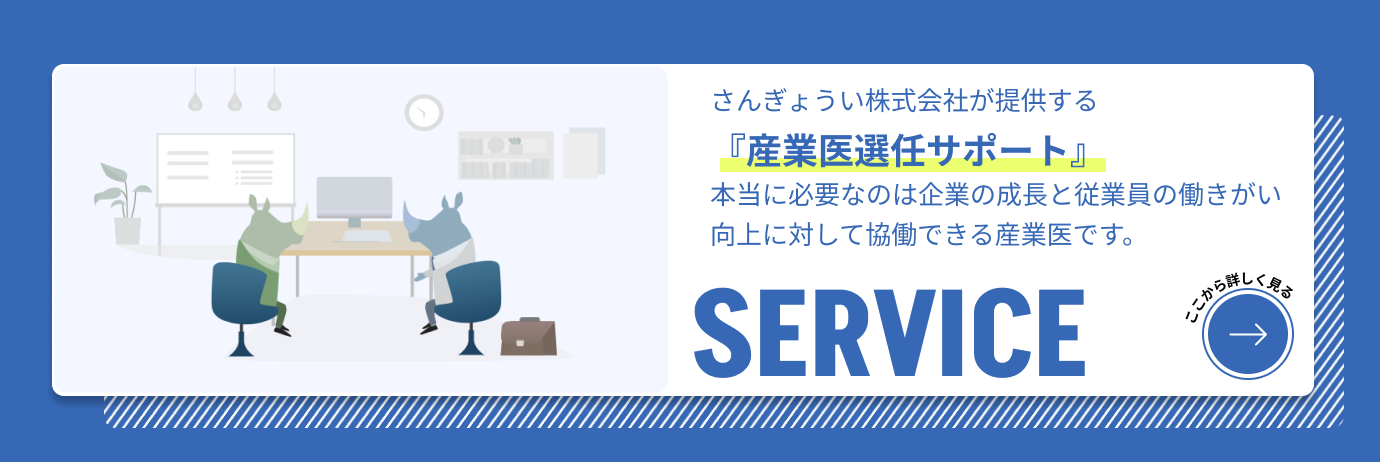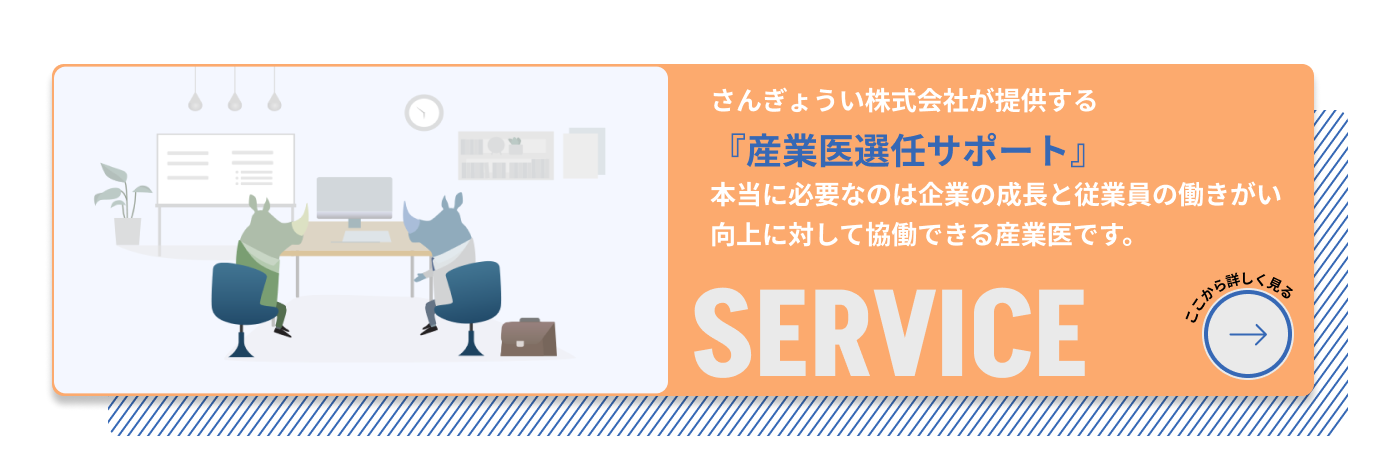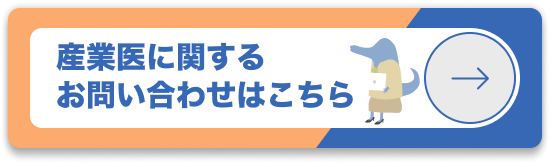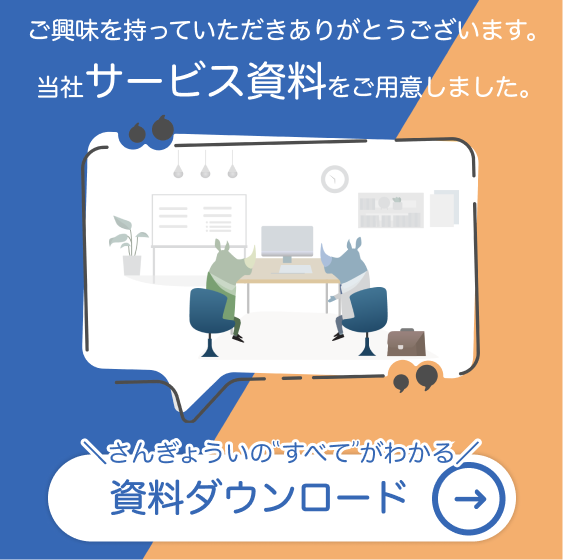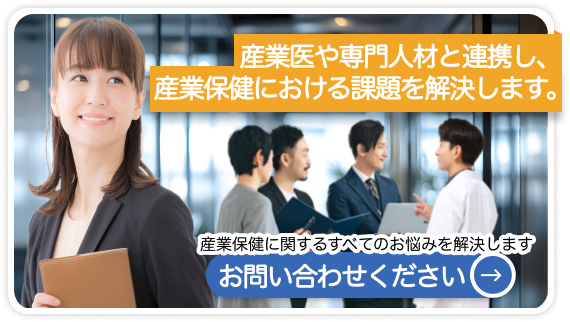ストレスのサインを見逃さない!ストレス対処法の徹底解説
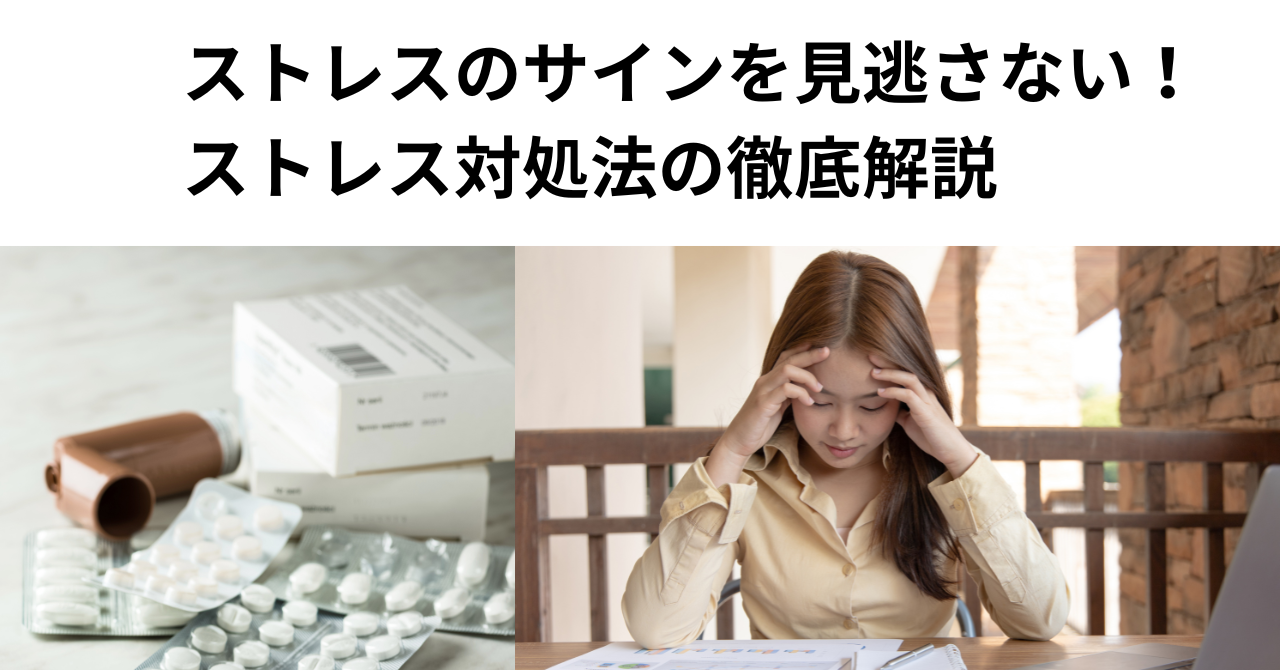
現代社会において、ストレスは多くの人々にとって避けられない問題となっています。心と身体の健康を維持するためには、ストレスのサインや症状を的確に認識し、適切な対処法を講じることが重要です。本記事では、ストレスのサインや症状、原因、ストレス対処法、そして予防策について詳しく紹介します。
目次
- ストレスとは?どのように自覚するか?
- ストレスの主なサインと症状とは?身体と心と行動にどのような影響を与えるか?
- ストレスの自覚が難しい時はどうすればいい?
- ストレスの原因は何か?職場や生活環境の影響
- ストレスから心身を守るための方法とは?
- 日常的にできるセルフケア
- 職場でできるセルフケア
- ストレスを感じやすい人の特徴とは?
- さいごに
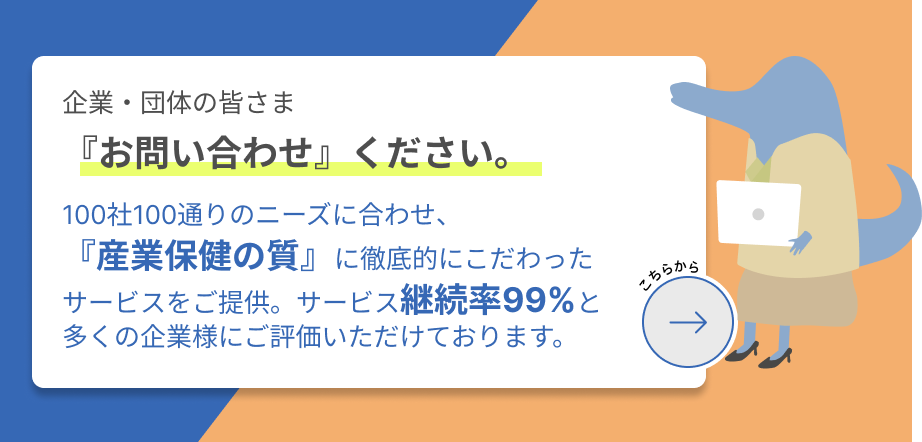
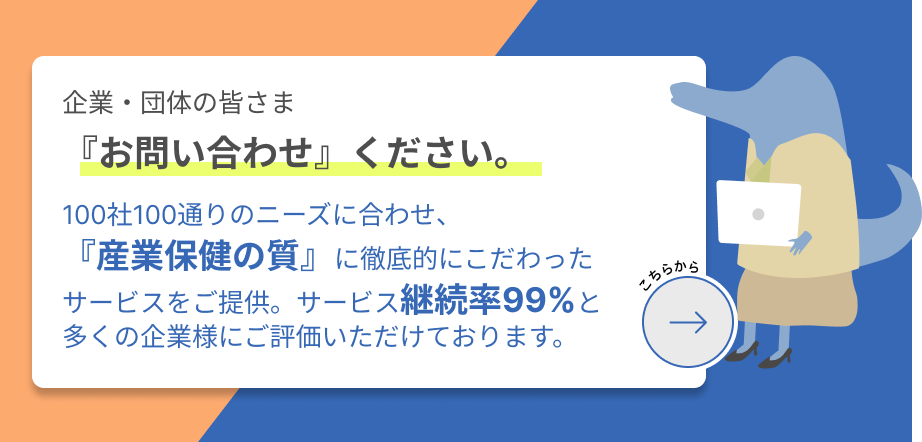
1.ストレスとは?どのように自覚するか?
・ストレスサインの例
ストレスとは、「日常生活の変化や出来事によって生じる緊張状態」のことを指します。例えば、イライラ感や不安感、集中力の低下、肩こり、頭痛、眠れないといった症状がストレスのサインとして挙げられます。こうしたサインを見逃さず、早期に気づくことで、ストレスが引き起こす病気のリスクを軽減できます。ストレスのサインを自覚することは、自分自身の健康を守るための第一歩と言えるでしょう。
・自分のストレスに気づくためのポイント
自分のストレスに気づくためには、まず日々の生活の中で自分の状態を観察することが大切です。心の状態や身体の不調、気分の変化や生活習慣などの行動の変化に注意を払いましょう。特に、仕事や家庭での問題が原因となることが多く、周囲の人間関係に影響を及ぼすことがあります。ストレスを感じる要因を知ることで、自分のストレス状態を理解し、適切な対処法を見つけることができるのです。
・ストレスサインを見逃さないために
ストレスサインを見逃さないためには、定期的に自分の心と身体をチェックする習慣をもつことが重要です。たとえば、日記をつけることで、自分の気分や体調の変化を記録できるので、ストレスの要因を把握する手助けとなります。また、信頼できる家族や友人に相談することもいいでしょう。他者の目を通して自分の状態を知ることで、より深く認識することができることもあります。
2.ストレスの主なサインと症状とは?身体と心と行動にどのような影響を与えるか?
・身体的なサイン
ストレスが身体に与える影響は非常に多岐にわたります。身体に現れる代表的なサインとして、頭痛や肩こり、胃腸の不調、睡眠障害などが挙げられます。また、ストレスが続くことで免疫力が低下し、病気にかかりやすくなることもあります。これらの症状は、ストレスによる体の反応であり、自律神経の乱れが原因となっていることも多いです。また、疲労感や倦怠感、食欲不振や過食など、日常生活に支障をきたすような変化が現れることもあります。これらの身体的なストレスサインに気づくことが自分のストレス状態を把握する上で重要です。
・精神的なサイン
ストレスは心に大きな影響を与えることは想像に難しくないでしょう。精神的なサインとしては、不安感や焦燥感、イライラ、落ち込みなどが挙げられます。これらの変化はストレスによる心の反応であり、これが強く継続するとメンタルヘルス不調を示す重要なサインとなり、うつ病や不安障害といった精神的な病気を引き起こす可能性があります。また、集中力の低下や記憶力の減退、決断力の低下なども精神的なストレスサインとして現れることがあります。特に、仕事に関することで強い不安、悩み、ストレスを抱えている労働者は多く、これが日常生活に悪影響を及ぼすことも珍しくありません。自分の気分や感情の変化に注意を払い、普段と異なる状態が長期間続く場合は、ストレスの影響を疑ってみる必要があります。
・行動的なサイン
ストレスは人の行動にも変化をもたらします。ストレスを感じている人は、普段はしないような行動を取ることが多くなります。たとえば、飲酒やタバコの量が増える、過度の飲食、運動不足などが挙げられます。これらの行動は、ストレス解消の手段として選択されることが多いですが、かえって健康を害する可能性があります。また、対人関係の悪化や仕事の能率低下、趣味や楽しみを避けるようになるなど、日常生活の様々な場面で変化が現れることがあります。このような行動の変化は、ストレスが持続することでさらにエスカレートする可能性があるため注意が必要です。
・ストレス関連疾患について
ストレスは、様々な身体的疾患のリスク因子となることが知られています。ストレス関連疾患として代表的なものには、胃潰瘍や十二指腸潰瘍などの消化器系疾患、高血圧や心疾患などの循環器系疾患、頭痛や筋肉痛などの痛み関連疾患があります。また、免疫系の機能低下による感染症のリスク増加や、皮膚疾患の悪化なども報告されています。これらの疾患は、ストレスが長期間続くことで発症や悪化のリスクが高まります。ストレス関連疾患の予防には、ストレスの適切な管理が不可欠です。定期的な健康診断の受診や、生活習慣の改善、後述するセルフケアの実践などを通じて、ストレスによる健康への悪影響を最小限に抑えましょう。
3.ストレスの自覚が難しい時はどうすればいい?
・ストレスチェックなどの活用
毎年社内で実施しているストレスチェックの結果をよく理解することはもちろんですが、日々のストレス状態を把握するためには、ウェブサイトなどで公開されているチェックリストを活用するのも有効です。自分のストレス状態を客観的に評価することもできるので、定期的にチェックリストを利用することで、ストレスの変化を追跡し、必要に応じて早めの対処をとることが可能になります。ただし、主観に基づく部分が大きいためチェックリストの結果だけで判断するのではなく、必要に応じて専門家への相談も検討しましょう。
・周囲からのフィードバック
自分ではストレスに気づきにくい場合もあるため、周囲の人からのフィードバックを得ることも重要です。家族や友人、職場の同僚、カウンセラーなど、日常的に接する人々の意見を聞くことで、自分では気づかなかったストレスのサインを発見できることがあります。たとえば、「最近イライラしているように見える」、「元気がないように感じる」といったコメントから自分の異変に気づくこともあります。周囲の人々と良好なコミュニケーションをとり、率直なフィードバックを得られる関係性を築くことが自分のストレスを把握する上で役立ちます。
4.ストレスの原因は何か?職場や生活環境の影響
・仕事のストレス
職場でのストレスは、「はたらく人」にとっては大きなストレス要因の一つです。残業や人間関係のトラブル、業務のプレッシャーなど、様々な要因が重なることもあるでしょう。このような仕事のストレスが長期間続くと、業務の効率や生産性にも悪影響を及ぼすだけではなく、欠勤や離職につながることがあります。「はたらくこと」に関する強いストレスが明らかであれば、ストレスを軽減するための取り組みを早急に考える必要があります。
・家庭のストレス
家庭環境もストレスの大きな要因になり得ます。家族間のコミュニケーション不足や経済的な問題、子育てや介護に関する悩みなどが挙げられます。家庭の中でのストレスは、家族全員が協力して問題解決に努めることが必要です。また、家族との時間を大切にし、困ったときには気軽に話ができるような良好な関係性を築くことがストレスの軽減につながります。
・日常生活に潜むストレス
日常生活には、意外にも多くのストレス要因が潜んでいますので、ここでいくつか具体例を挙げてみます。交通渋滞や満員電車、家庭内の雑事、空調の効きが悪くてじっとしていても暑すぎたり、寒すぎたりなど、一日を思い返してみると些細なことでもストレスを感じることはあると思います。このような出来事の一つひとつは小さなことのように感じられるため、目を向けていない方も多いかもしれませんが、これらは積み重なることで大きな負担となり、心身の健康を損なう要因となります。日常生活を見直し、自分自身がストレスを感じることは何なのか、ストレスの元を把握しましょう。
5.ストレスから心身を守るための方法とは?

・セルフケアの重要性
ストレスで体調不良を引き起こさないためにはセルフケアへの取り組みが重要です。自分の心と身体を労わる時間をもつことは、ストレスの軽減と健康維持につながります。休日の過ごし方を工夫したり、趣味の時間を設けたり、リラックスできる環境を整えたりすることが効果的です。また、自分の好きなことに没頭することで、日常のストレスによって疲弊した心を回復させられるでしょう。セルフケアはやった分だけ楽になるはずです。何をセルフケアとすればいいのかよく分からないという方は、これより先に載せている実践方法を参考にぜひ少しずつでも実際に「取り組む」ことをしてください。
・ストレス解消に役立つ生活習慣
健康的な生活習慣を維持することも、セルフケアの重要な要素です。バランスの取れた食事や十分な睡眠、適度な運動は心身の健康を保つ基盤となります。特に、睡眠不足はストレスを増加させるどころか様々な健康問題を引き起こします。後述しますが質の良い睡眠を確保することが大切です。また、適度な運動はストレスホルモンの低下に寄与するため、「はたらく人」のメンタルヘルス不調を予防する方法として挙げられます。
6.日常的にできるセルフケア
・メンタルヘルスの“いい状態”を維持するための方法
効果的なセルフケアには日常的な心のケアが欠かせません。自分の感情を理解し、日々表現する機会をもつことが効果的です。日記をつけるなど自分一人で取り組むこともいいですし、一人で難しい場合はカウンセリングなどを利用し、定期的に専門家に話すことも一つの方法です。
・適度な運動と睡眠
適度な運動と十分な睡眠は非常に効果的です。運動をすることで、体内でセロトニンなどの幸せホルモンが分泌され、気分を前向きにする効果が期待できます。ジョギング、ウォーキング、ヨガなど、自分に合った運動を定期的に行うことで、セルフケアにつながります。また、規則正しい睡眠習慣を身につけることはもちろん大切ですが、就寝前にリラックスタイムを設けたり、自分が寝やすいように睡眠環境を整えたりするなど、質の良い睡眠を得るための工夫も重要です。
・リラクセーション法
リラクセーション法を日常生活の中に取り入れることはストレス対処に非常に効果的です。深呼吸や瞑想、ヨガ、自律訓練法などのリラクセーション法は、ストレスによる緊張を和らげ、心を落ち着かせる効果があるので心の安定を図るのに役立ちます。多忙な日々をお過ごしのことと思いますが、短時間でもこのような自分の時間をもつことが、ストレス解消につながります。ストレスを感じた際に、すぐにリラクセーション法を実践できるよう、自分に合った方法を探しておくことをおすすめします。
・趣味や楽しみの時間を作る
日々の生活の中で、自分が楽しいと感じる活動に時間を割くことで、ストレスから一時的に開放され、心身のリフレッシュにつながります。趣味は創造性を刺激し、自己表現の機会になるだけではなく、達成感や満足感を得ることにもつながります。読書、音楽鑑賞、ガーデニング、料理、絵画など、自分に合った趣味を見つけることが大切です。また、友人や家族と過ごす時間も、ストレス解消に効果的です。楽しい会話や共有体験は、ポジティブな感情を促進し、ストレスを軽減します。日常生活の中に、これらの楽しみの時間を意識的に組み込むなど、休み方に工夫をしながら過ごすことをレジャークラフティング(詳しくはコチラ)と言いますが、このように自分時間の作り方を意識することもセルフケアに繋がります。
7.職場でできるセルフケア
・タイムマネジメントの改善
仕事の締め切りに追われたり、時間効率を上げなければならなかったり、時短を求められたり、といった時間に関する重圧は大きなストレス要因となることがあります。私たちはこのように時間に縛られている環境の中で働かなければならないのですが、効率的なタイムマネジメントを行うことで、これらのストレスを軽減することができます。具体的には、優先順位をつけて仕事を整理する、タスクリストを作成する、集中力が高い時間帯に重要な仕事を行うなどの方法があります。また、適度な休憩を取ることも重要です。短い休憩を定期的に挟むことで、集中力を維持し、ストレスの蓄積を防ぐことができます。自分に合ったタイムマネジメント法を見つけ、実践することで、職場でのストレスを上手くコントロールすることが可能になります。
・職場内でのコミュニケーション
職場で良好なコミュニケーションがとれるかどうかといった感覚はストレス対処に非常に重要な要素です。良好な人間関係を築くことで、職場の雰囲気が改善され、ストレスの軽減につながります。周囲と適切にコミュニケーションを取ることで、問題の共有や解決策の検討が可能になり、一人で抱え込んでしまうことを防ぎます。また、困難な状況に直面した際に、サポートを得やすくなるというメリットもあります。定期的なミーティングやチームビルディング活動に参加することで、周囲との関係性が強化され、「働きやすい」環境づくりにつながるでしょう。
・ワークライフバランスの見直し
仕事と私生活のバランスが崩れると、セルフケアが難しくなります。適切なワークライフバランスを保つために、まずはやはり自分の現状を把握し、必要に応じて改善策を講じることが大切です。たとえば、上述したようなタイムマネジメントを実践して残業を減らす、休日は仕事のことを考えないようにする(距離を置く)、趣味や家族との時間を確保するなどの方法があります。また、職場の制度を活用することも有効です。フレックスタイムや在宅勤務など、柔軟な働き方を取り入れることも可能であれば検討するとよいでしょう。ワークライフバランスの見直しは、長期的な視点で取り組むことが重要であり、自分に合った方法を見つけていくことが大切です。
8.ストレスを感じやすい人の特徴とは?
・パーソナリティタイプ
ストレスの感じやすさは、個人のパーソナリティタイプと密接に関連しています。たとえば、完璧主義や高い基準を自分に課す傾向がある人は、ストレスを感じやすいことが知られています。また、ネガティブな思考パターンを持つ人や、変化に適応しにくい人もストレスを感じやすい傾向があります。一方で、楽観的で、柔軟性のある思考をもつ人は、ストレスへの耐性が高い傾向があります。自分のパーソナリティタイプを理解し、ストレスとの関連性を認識することで、より効果的なセルフケアが可能になります。ただ、パーソナリティタイプはあくまでも傾向であって、個人差は大きいことに留意する必要があります。自己理解を深めつつ、自分に合ったストレス対処法を見つけていきましょう。
・環境要因との関係
個人を取り巻く環境要因もストレスの感じやすさと関連しています。たとえば、サポート体制が不十分な場合や、孤立感を感じやすい環境にある人はストレスの影響を受けやすいでしょう。一方で、良好な人間関係や、適度な挑戦と成長の機会がある環境ではストレス耐性が高まる可能性があります。環境を変えることが難しい場合でも、これまでご紹介したようなストレス対処法を実践することで、ストレスの影響を軽減することができます。
9.さいごに
ストレスによる健康への影響を予防するためには、自分でできる早めの対処と必要に応じた専門家への相談が重要です。ストレスによる異変に気づいたら、できるだけ早い段階で自分に合ったセルフケアを実践しましょう。セルフケアを試してみても改善がみられない場合や、ストレスが日常生活や業務に支障をきたすほど深刻な場合は、躊躇せずに専門家に相談することをおすすめします。産業医、心療内科や精神科の医師、産業保健師や臨床心理士などの専門家は、個々の状況に応じた適切なアドバイス、もしくは治療を提供することができます。また、職場のメンタルヘルス相談窓口や厚生労働省が運営している「こころの耳」の相談窓口でサポートを受けることもできます。早期の対処と専門家の支援を受けることで、ストレスによる健康への悪影響を最小限に抑え、より良い生活を送ることができるでしょう。
ストレス対策は「自分を大切にすること」から始まります。忙しい毎日の中で、ほんの少しだけでも自分を労わる時間を作ってみてください。その小さな一歩が、きっとみなさんの心と体を軽くしてくれるはずです。
(参考)
・Jing Hu , Baojuan Ye , Murat Yildirim , Qiang Yang . (2023). "Perceived stress and life satisfaction during COVID-19 pandemic: the mediating role of social adaptation and the moderating role of emotional resilience." Psychol Health Med, 28(1):124-130.
・Kimyai-Asadi, A., & Usman, A. (2001). "The Role of Psychological Stress in Skin Disease." Journal of Cutaneous Medicine and Surgery, 5(2), 140-145.
・厚労省 令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)
・Segerstrom, S. C., & Miller, G. E. (2004). "Psychological Stress and the Human Immune System: A Meta-Analytic Study of 30 Years of Inquiry." Psychological Bulletin, 130(4), 601-630.
・Susan Abraham (2024). "Work-Life Conflict and Work Stress: The Mediating Role of Personality." International Research Journal on Advanced Engineering and Management (IRJAEM).
・Weixi Kang, Francois Steffens, Sònia Pineda, Kaya Widuch & Antonio Malvaso (2023). "Personality traits and dimensions of mental health." Scientific Reports volume 13.
【動画研修】レジャークラフティング ー心理士も実践する効果が上がる休み方の工夫ー 詳細はこちら【動画研修】心と体のバランスを整える ー自律訓練法を用いてー 詳細はこちら
【動画研修】ストレスとは②ストレスに対処する 詳細はこちら
大学院では精神分析学を専攻とし、大学院修了後は精神科にて約5年の臨床経験を積む。
現在は企業向けにストレスチェックの分析や面談、メンタルヘルス関連の研修などを行い、様々な形で企業を支援する。